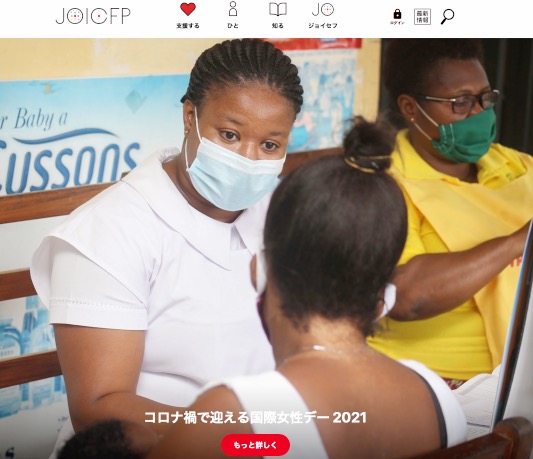自然災害のあった地域や国に対して行われる復興支援。
支援物資などを運んだりボランティアで食事を作ったりしている様子を、ニュースや報道で目にしたことはあると思います。
しかし、復興支援をしたいとは思うものの
「実際にどのようなことが行われているのか詳しく知らない」
「どのように行動したら良いか分からない」
という方もいると思います。
そこでこの記事では以下の内容をご紹介します。
- ・どのような復興支援が行われているのか
- ・どのように復興支援に関われるか
- ・復興支援へ寄付できるおすすめの団体
復興支援は長期にわたって必要です。また、再度発生した際に被害を最小限に抑えるための取り組みも大切です。
継続的な寄付をはじめ私たちにできることは様々です。
支援に興味のある方は、ぜひ本記事の内容を役立ててみてください。
早速、日本や海外で復興支援活動をしている団体を知りたい方はこちら。
>>復興支援活動をしているおすすめの寄付先団体を6つ紹介
能登半島地震の被災者への寄付を考えているあなたへ
被災地では様々な団体が支援活動を行っています。
寄付は、私たちがいますぐ行動に移せる支援です。
寄付を受け付けている団体や、行われている支援活動を詳しく解説します。
復興支援とは?

自然災害の支援には、それぞれの局面(フェーズ)に応じた支援が求められます。
復興支援とは「生命の危険は去り、復興に向けての活動期における段階」の支援活動を指します。
災害発生後のフェーズと求められる支援は以下の通りです。
- ・初動期(災害発生当日)
救命活動や行方不明者の捜索など「いのちを守る活動」が行われます。 - ・応急期(災害発生~1週間程度)
被害の拡大を防止する活動が優先される。ニーズ調査、物資支援、避難生活者の心や健康面のケアが行われます。 - ・復旧期(1週間~1ヶ月)・復興期(1ヶ月以降)
財産と環境の保全が行われます。被災前の生活に戻るべく、生活再建のための活動が行われます。
※期間は目安です。
復興支援は、被災地が被災前よりさらに発展している状態、防災・減災をより強化した状態を目指します。
参考:
内閣府 防災情報のページ「地⽅公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」
内閣府 防災情報のページ「地方都市等における地震対応のガイドライン 」
復興支援にはどんな種類がある?

復興支援とは、自然災害が起こってから数ヶ月後に行われ、被災した人々が自力の生活へと移行できるようにサポートするためのものです。
当日から3日後あたりに行われるのは、人命の救助やがれきの撤去といった緊急支援(救命支援)となります。
災害に遭った後は、命が助かったとしても家を直して住む場所を確保したり、仕事を確保したりしなければ普段の生活には戻れません。
そのような状況の中でサポートをするのが復興支援です。復興支援には、以下のような種類があります。
- ・健康管理のサポート
- ・家屋修復
- ・中長期的な避難場所および備品の確保
- ・インフラ整備
- ・こころのケア
- ・コミュニティの形成
- ・生計立て直しおよび産業復興
- ・災害対策の強化
内容について詳しく見ていきましょう。
健康管理のサポート
被災後、慣れない避難生活の中で健康状態が悪化することがあります。
衛生状態の悪いトイレの利用を控えたり、慣れない避難所で睡眠不足に陥ったり、限られた食材で作る食事で栄養不足になったりするのです。
これらが原因で、感染症や循環器系の疾患を患ったり、高血圧を発症したりします。最悪の場合は死に至ってしまう場合もあります。これは災害関連死と呼ばれ、特に高齢者に起こりやすいです。
こうした健康被害や災害関連死を防ぐために、健康相談や医療従事者の巡回、バランスの取れた食事を提供する炊き出しなどが行われています。
例えば、 AAR Japan[難民を助ける会]は、避難所で過ごす人たちに向け、出張マッサージや、移動式お風呂カーで入浴サービスを提供しています。
家屋修復
災害などで失われた家を建て直したり新しく建てたりする支援も行われています。国からの補助はありますが、それだけでは家を建て直すには足りないのです。
例えば、ピースウィンズ・ジャパンでは、自然災害などで失われた家屋の修繕を支援しています。国内での支援も多く行われており、台風などで壊れた家の修繕をサポートしている団体の1つです。
中長期的な避難場所および備品の確保
中長期の生活を見越した避難場所と備品の確保も必要です。
緊急時に使われる避難所の多くは学校です。学校が再開されると避難所を閉じる必要があります。自宅に帰れない人たちのために、新たな避難所を確保したり避難所を集約する必要があります。また仮設住宅に入居する人もいます。
避難所では、避難生活が長くなった被災者が心身共に健康に過ごせるよう、簡易ベッドや仕切りなどの備品の確保が必要です。また避難者が集う共有スペースに置く、机や椅子なども必要になります。
仮設住宅では、個人宅に家電製品などが新たに必要になります。
例えば、ピースウィンズ・ジャパンでは、避難所の閉鎖に伴い、新しい避難所のレイアウトの作成、設営、物資調達・搬入、環境整備まで、立ち上げを全面的にサポートしています。希望者からのヒアリングも行い、それぞれの人の希望に沿った環境づくりを手伝っています。
>>ピースウィンズ・ジャパンについての解説へ移動する
インフラ整備
がれきや亀裂の発生などで通行できなくなった道路の修復、ガス、水道、電気といったライフラインの復旧が行われます。
個人宅周辺の道路のがれき撤去などは住民やボランティアの手によって行われる場合もありますが、多くの場合インフラ整備は自治体が担います。
こころのケア
災害に巻き込まれた人々は心に深く傷を負っており、中にはトラウマを抱えてしまう方もいます。このような人々に対し、話を聞いたり不安を軽減したりする「こころのケア」が行われています。
例えば、ワールド・ビジョン・ジャパンでは、被災した子どもが思いっきり遊べるイベントを開催したり、子どもの居場所づくりを行っています。他にも、保育士、保護者など、子どもと接することが多い大人に向け、PFA(心理的応急処置)研修を実施しています。
>>ワールド・ビジョン・ジャパンについての解説に移動する
コミュニティの形成
自宅に残る人、避難所で生活する人、遠方に避難する人など、被災によりコミュニティの顔ぶれに変化が起きます。
社会とのつながりを失ってしまう人が出てきてしまい、孤独死するお年寄りが懸念されます。また、被災前の生活に戻るには地域の人々の結びつきの強さが重要です。
人々が安心して生活するためにも、地域が早い復興を遂げるためにも、新たなコミュニティの形成が必要になります。人々が交流できる場所や、住民ボランティアグループの形成などが支援団体により行われます。
例えば、ジョイセフでは、被災した母子が集い安心して過ごせる交流サロンの運営の支援を行っています。
>>ジョイセフについての解説へ移動する
生計立て直しおよび産業復興
産業および生計を立て直し、地域や人々の生活基盤を再建する必要があります。
広い範囲での地域の産業復興への取り組みは行政によって行われることが多いです。個人や小さなコミュニティの生計立て直しにおいては、支援団体が大型設備の購入資金を援助したり、新たに始めるビジネスの相談に乗ったり、PR活動をサポートしたりしています。
災害対策の強化
自然災害が再発生した際の被害を最小限に抑えるために、災害対策の強化が行われています。
津波防御堤などインフラの整備や、新たな居住可能地域の選定などは主に行政によって行われます。
NPO等の支援団体では
・避難方法を事前に地域で取り決める
・避難訓練を行う
・防災マップを作成
など二次災害を回避するための取り組みの支援活動が行われています。
復興支援のために私たちができること

復興支援のために私たちができることには、以下のようなものがあります。
- ・支援団体にお金の寄付をする
- ・復興支援商品を買う
- ・復興支援旅行に行く
- ・ボランティアとして復興支援に関わる
- ・モノの寄付をする
私たちにできる復興支援には様々な方法があります。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
支援団体にお金の寄付をする

今すぐにどこからでも支援できる方法として支援団体へのお金の寄付があります。
長期的に支援したい方には継続寄付がおすすめです。復興支援は時間がかかるため、長期的な支援を必要としている団体がほとんどです。
また、多くの団体は継続寄付者に活動報告を行っており、支援の効果を実感することができます。お金の寄付は、寄付金控除が適用される場合があります。寄付金控除については以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひあわせて参考にしてみてください。
>>寄付金控除の仕組みとは?確定申告の方法も紹介
復興支援商品を買う

商品を購入することで被災地の支援ができます。
方法の1つとして、被災地で生産されている商品の購入があります。その地域に収入や雇用の創出をもたらすだけでなく、商品によっては文化や歴史を守ることにもつながります。
また、収益の一部が復興支援に使われる商品を購入する方法もあります。企業の社会貢献活動として行われている場合が多いです。商品の収益の一部が、その企業が行う支援活動に活用されたり、復興支援を行う団体に寄付されたりします。
復興支援旅行に行く

復興支援旅行に行くことでも被災地の支援ができます。
方法の1つとして、被災地に観光に行く方法があります。被災地が旅行者を受け入れる状態にある状態にあることが前提となります。現地で観光したり、商品を購入したりしてお金を使うことで、地元経済の活性化に貢献できます。
政府や旅行会社が、被災地への旅行の割引キャンペーンなどを行う場合もあります。
また、復興支援旅行がもたらすものは、被災地の経済活性だけではありません。旅行者が被災地を実際に自分の目で見て、その様子を周囲に伝えることで、人々の記憶を風化させないという効果もあります。
モノの寄付をする

モノの支援は、実際に自分の手元から被災地にモノを送るので、役に立っている実感が持てるのが特徴です。
初動期や応急期は、被災地の混乱により物流が滞り、物資が手に入らない場合があります。しかし、状況がある程度落ち着いた復興期は、生活用品は足りていることがほとんどです。
復興期は、コミュニティスペースや新たな避難場所の整備が行われ、パソコンやテーブルといった高価な備品が必要なことが多いです。また、椅子や食器など、人が集まるスペースで複数個のものが必要になります。
個人的な繋がりでの寄付は、依頼される可能性はありますが、それ以外は団体や企業でないと手配するのがなかなか厳しい場合があります。
それでももちろん被災地では物品のニーズがあります。モノの寄付を希望する場合は、事前に寄付先と綿密なコミュニケーションを取って、必要なものを必要なタイミングで届けるように心がけましょう。
モノの寄付に関しては下記の記事で詳しく説明しているのでぜひ参考にしてください。
>>食料や服の寄付は支援に役立てにくい?実際のところを専門家が解説!
ボランティアとして復興支援に関わる

直接、被災地などにいって現地のボランティアとして復興支援に関わる方法もあります。現地に出向けない人には、支援団体のオフィス業務を手伝う方法もあります。
繰り返し現地に行って支援をすれば、被災地が徐々に復興していく様子を実感できます。ただし、ボランティアを行う場合には、時間と場所の制約があることを覚えておきましょう。
支援団体や被災自治体の災害ボランティアセンターを通して参加すると、トラブルや、現地の負担になることを防げます。
災害の復興支援活動をしているおすすめの寄付先団体を6つ紹介
ここからは「復興支援に取り組むNPO団体に寄付したい」と考えている方に向けて、おすすめの寄付先団体を6つご紹介します。NPOの専門家の注目ポイントも参考にしてください。
【復興支援活動をしている団体6つ】

認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン:人道支援や災害支援の分野で20年以上の経験を持つ日本発祥のNGO
ピースウィンズ・ジャパンは、国内外で自然災害、あるいは紛争や貧困などによる人道危機や生活の危機にさらされた人びとを、教育、水衛生、保健、シェルター、生計向上、弱者保護、物資配布などの分野で支援しています。
震災や豪雨の被災地では、コミュニティ再生や地域集会所の運営支援を5年~10年といった期間にわたって継続しています。
また、国内において保護犬の里親探しや譲渡を促進するプロジェクト「ピースワンコ・ジャパン」の展開や、緊急災害支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団」の運営を行っています。
日本発祥の国際NGOで、これまで33か国で活動を行ってきています。
ピースウィンズ・ジャパンは広島県より認定NPOの認証を受けています。
また、優れたソーシャルビジネスの取り組みを表彰する、日経ソーシャルイニシアチブの受賞歴もあります。
活動を通し、人びとが紛争や貧困などの脅威にさらされることなく、希望に満ち、尊厳を持って生きる世界を目指しています。
【どんな人に向いてる?】gooddo編集部が考えてみました
- すぐに人の役に立つ活動に寄付したい!という方
災害支援がメインということもあり初動が速く、支援が実行されるまでの時間が短いです。 - 支援内容の報告をしっかり受けたい!という方
ピースウィンズ・ジャパンは活動の報告を頻繁に行っています。特にYouTubeでの報告は現地の様子や活動の詳細が分かりやすいです。 - 寄付の効果を実感したい!という方
ピースウィンズ・ジャパンの主な支援分野の一つである自然災害は、日本でも多く発生しており、自分の身近なところでいつでも起こり得ます。遠くの国のできごとでも、日本に住む私たちにも支援地の変化の様子がイメージしやすいです。
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら
>>【実際どう?】「ピースウィンズ・ジャパン」の気になる口コミ評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
特定非営利活動法人 難民を助ける会(AAR Japan):保健衛生、教育、障がい者支援分野で復興への継続的なサポートを行う
AAR Japan[難民を助ける会]はこんな人にオススメ!
- ・日本発の難民支援活動を行っている団体を応援したい
- ・40年の長い歴史がある信頼できる団体に寄付したい
- ・国連に公認・登録されているなど国際的に評価された団体に安心を感じる
AAR Japan[難民を助ける会]は世界14カ国で紛争・自然災害・貧困などにより困難な状況に置かれている人々を支援しています。現在は日本の他にアジア、中東、アフリカの12の国に事務所を持ち、難民支援や地雷不発弾対策などの活動を行っています。
復興支援として、被災者に寄り添う心身のケアや、再び学校や障がい者施設に通う日常に戻れるような地域への中長期的なサポートなどを行っています。
活動を通し、一人ひとり多様な人間が、各々の個性と人間としての尊厳を保ちつつ共生できる、持続可能な社会を目指しています。
寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!
- 1979年に日本で発足以来、活動地域や分野を広げながら65を超える国・地域で支援を展開してきた実績あり
- 1998年には、国連経済社会理事会(ECOSOC)の特殊協議資格を取得し、国連に「公認・登録」されている
- 「人道」「公平」「独立」「中立」の人道4原則に則り、AAR Japan[難民を助ける会]が大切にする「行動規範や社会的責任・人権方針」を掲げる
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら
>>【実際どう?】AAR Japan[難民を助ける会]の気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
>>AAR Japan[難民を助ける会]に関する記事一覧はこちら
認定NPO法人 カタリバ:被災地の子どもたちに学びの場を提供
カタリバはこんな人にオススメ!
- ・教育の可能性や重要性を信じている
- ・実績や社会的な信頼は大事だと思う
- ・家庭や学校で困難を抱える子どもでも、成長の機会を得られる社会になってほしい
カタリバは、自身ではどうすることもできない家庭環境などの課題を抱える子どもたちを対象に、居場所・学習・食事を地域と連携しながら届ける活動などを行っています。
復興支援としては、放課後学校「コラボ・スクール」を立ち上げ運営。子どもたちが落ち着いて万安打り安心して過ごせる居場所を提供しています。
活動を通じて「すべての10代が意欲と創造性を育める未来」の実現を目指しています。
寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!
- 2011年7月、東日本大震災で被災した子ども達のために放課後の学校を、被害が最も激しかった宮城県女川町と岩手県大槌町に開設。学ぶ場の提供とともに震災で傷ついた心のケアも実施。また近年は、令和元年台風19号、令和2年7月豪雨、令和3年7月伊豆山土砂災害の被災地の子どもたちに対して「安心して過ごせる居場所の提供と学習支援」を実施。
- 子どもたちのコメントから「勉強だけでなく生き方への影響や将来の夢を後押しすること」につながっていることがうかがえる
- 「意欲と創造性をすべての10代へ」というミッションを掲げ、貧困や不登校、災害など困難さを抱えていたり、自己肯定感が低く意欲が持てない10代に対して、18年間教育活動に取り組んでいる実績
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら
>>【実際どう?】カタリバの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン:子どもが健やかに成長できる生活基盤を取り戻す支援
ワールド・ビジョン・ジャパンはこんな人にオススメ!
- ・寄付をした効果が継続して実感できる方が良い
- ・子どもの顔が見える関係で支援したい
- ・具体的な数字があるとわかりやすく感じる
ワールド・ビジョン・ジャパンは、約100カ国において保健、水衛生、生計向上、教育、栄養の分野での開発援助や緊急人道支援を通して、困難な状況で生きる子どもたちのために活動しています。
災害の復興支援としては、子どもたちが健やかに成長できる生活基盤を取り戻すための支援を、保健・栄養、子どもの保護、子どもへの教育などの分野において行っています。また、精神的に不安定になってしまう子どもたちのために、子どもたちが自由に過ごせる「チャイルド・フレンドリー・スペース」の運営もします。
国連機関に公認・登録された世界最大級の子ども支援専門の国際NGOです。
寄付アドバイザー河合さんの注目ポイント3つ!
- 途上国の子どもと心のつながりを持ちながら支援する「チャイルド・スポンサーシップ」が特徴
- 「何もかもはできなくとも、何かはきっとできる」などのメッセージから団体が大切にしていることが伝わる
- 「極度の栄養不良にあった子どもたちの89%が完全に改善」など、活動の影響を具体的な数字で示している
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら
>>【実際どう?】ワールド・ビジョン・ジャパンの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
公益財団法人ジョイセフ: ニーズが見落とされがちな女性と母子を対象とした復興支援を行う
ジョイセフは、世界各国において、母子保健向上、家族計画と避妊、女性のエンパワーメント、緊急復興支援などの分野で活動しています。
保健医療サービスの提供による妊産婦死亡の削減や、少女たちに対する家族計画に関する知識などを通して、命と健康が「格差」によっておびやかされている途上国の女性を支援しています。
復興支援においては、弱い立場に置かれ支援のニーズが見落とされがちな女性と母子を対象に活動。母子が集まり安らげる場や、助産師による産前産後ケア、カウンセリングなどを提供しています。
ジョイセフでは、持続可能なコミュニティをつくるためには「人づくり」が重要だと考え、地域の人材育成を活動の中心としています。
活動を通じて、「すべての人びとが自らの健康を享受し、尊厳と平等のもとに自己実現できる世界」を目指しています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- 日本において、家族計画、女性のエンパワーメントを中心とした保健分野の国際協力における最長の歴史と最大の実績を有する専門機関
- 日本で役目を終えたランドセルをアフガニスタンに寄贈し、子どもたち特に教育の機会に恵まれない女の子の就学に役立てる「思い出のランドセルギフト」は特徴的な取組み
- 「ジョイセフアンバサダー」に冨永愛さんが就任し広報リーダーの役割を果たす
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら:【実際どう?】ジョイセフの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
一般社団法人ピースボート災害支援センター:10万人以上がボランティアに参加
2011年の設立以来、海外31ヶ国・国内54地域での被災地支援を実施。復興支援としては、漁業・水産業の担い手の創出、交流人口の増加、移住定住の促進など被災地の人たちとともに地域課題に取り組んでいます。
現場経験を活かした研修や訓練を実施し、防災・減災教育にも力を入れています。
「すべての人々が互いに助け合える社会」を目指しています。
- 被災した地域で共に活動したボランティアの延べ人数が105,590人にも上る実績
- 「人こそが人を支援できるということ」「「お互いさま」を共に歩む、など印象に残るメッセージ
- 私たちができることには「備える・学ぶ」もあり、経験や教訓を生かした教材や学びの機会もこの団体ならではのもの
このように考えている方は、この機会に遺贈寄付を考えてみませんか?
生前に手続きを済ませるだけで、自分の遺産を支援団体に寄付(遺贈寄付)できます。
遺贈寄付先の選び方をチェックする
まとめ:復興支援は継続的に必要な活動!私たちにもできることから始めよう

この記事の内容をまとめます。
- ・復興支援は、被災地が被災前よりさらに発展している状態、防災・減災をより強化した状態を目指している
- ・さまざまな復興支援活動が行われていて、どれも長期に渡って続けていく必要がある
- ・私たちにできる復興支援にはお金の寄付はじめ色々な方法がある
復興支援をすることは簡単なことではありませんが、長期的なサポートが多くの人を救います。支援を行っている団体も多いので、ぜひ本記事を参考にしながら自分の目的や希望に合うところを選んでみてください。
以下の記事では災害時の緊急支援活動を寄付で支える方法を紹介しています。興味がある方はぜひご一読ください。
>>災害支援活動に寄付しよう!寄付金控除も適用できる団体5選
▼復興支援活動を行う団体
| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |
|---|---|
| ピースウィンズ・ジャパン | 【どんな人に向いてる?】 ・すぐに人の役に立つ活動に寄付したい!という方 ・支援内容の報告をしっかり受けたい!という方 ・寄付の効果を実感したい!という方 |
| AAR Japan[難民を助ける会] | ・1979年に日本で発足以来、活動地域や分野を広げながら65を超える国・地域で支援を展開してきた実績あり ・1998年には、国連経済社会理事会(ECOSOC)の特殊協議資格を取得し、国連に「公認・登録」されている ・「人道」「公平」「独立」「中立」の人道4原則に則り、AAR Japan[難民を助ける会]が大切にする「行動規範や社会的責任・人権方針」を掲げる |
| カタリバ | ・2011年7月、東日本大震災で被災した子ども達のために放課後の学校を、被害が最も激しかった宮城県女川町と岩手県大槌町に開設。学ぶ場の提供とともに震災で傷ついた心のケアも実施。また近年は、令和元年台風19号、令和2年7月豪雨、令和3年7月伊豆山土砂災害の被災地の子どもたちに対して「安心して過ごせる居場所の提供と学習支援」を実施。 ・子どもたちのコメントから「勉強だけでなく生き方への影響や将来の夢を後押しすること」につながっていることがうかがえる ・「意欲と創造性をすべての10代へ」というミッションを掲げ、貧困や不登校、災害など困難さを抱えていたり、自己肯定感が低く意欲が持てない10代に対して、18年間教育活動に取り組んでいる実績 |
| ワールド・ビジョン・ジャパン | ・途上国の子どもと心のつながりを持ちながら支援する「チャイルド・スポンサーシップ」が特徴 ・「何もかもはできなくとも、何かはきっとできる」などのメッセージから団体が大切にしていることが伝わる ・「極度の栄養不良にあった子どもたちの89%が完全に改善」など、活動の影響を具体的な数字で示している |
| ジョイセフ | ・日本において、家族計画、女性のエンパワーメントを中心とした保健分野の国際協力における最長の歴史と最大の実績を有する専門機関 ・日本で役目を終えたランドセルをアフガニスタンに寄贈し、子どもたち特に教育の機会に恵まれない女の子の就学に役立てる「思い出のランドセルギフト」は特徴的な取組み ・「ジョイセフアンバサダー」に冨永愛さんが就任し広報リーダーの役割を果たす |
寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー
大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。
寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。
国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。