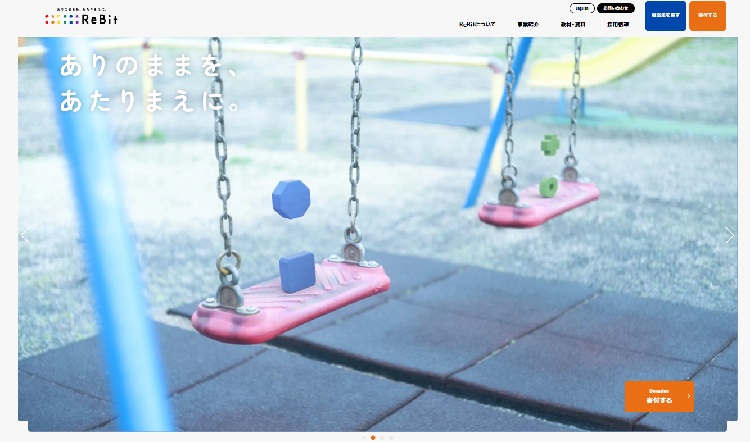「ポリコレ(ポリティカルコレクトネス)とはどういう意味だろう」
「ポリコレ(ポリティカルコレクトネス)は社会にどのような影響を与えたのだろうか」
このように疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。そこで本記事では下記の内容についてご紹介します。
- ・ポリティカルコレクトネスの定義
- ・ポリティカルコレクトネスの具体例
- ・ポリティカルコレクトネスの弊害
ポリコレ(ポリティカルコレクトネス)は私たちの生活だけでなく、学校や企業活動にも影響を与えている考え方です。ただし一部では行き過ぎたポリティカルコレクトネスによる弊害も指摘されています。ポリティカルコレクトネスについて理解を深めたい方はぜひ読んでください。
ポリティカルコレクトネスとは?
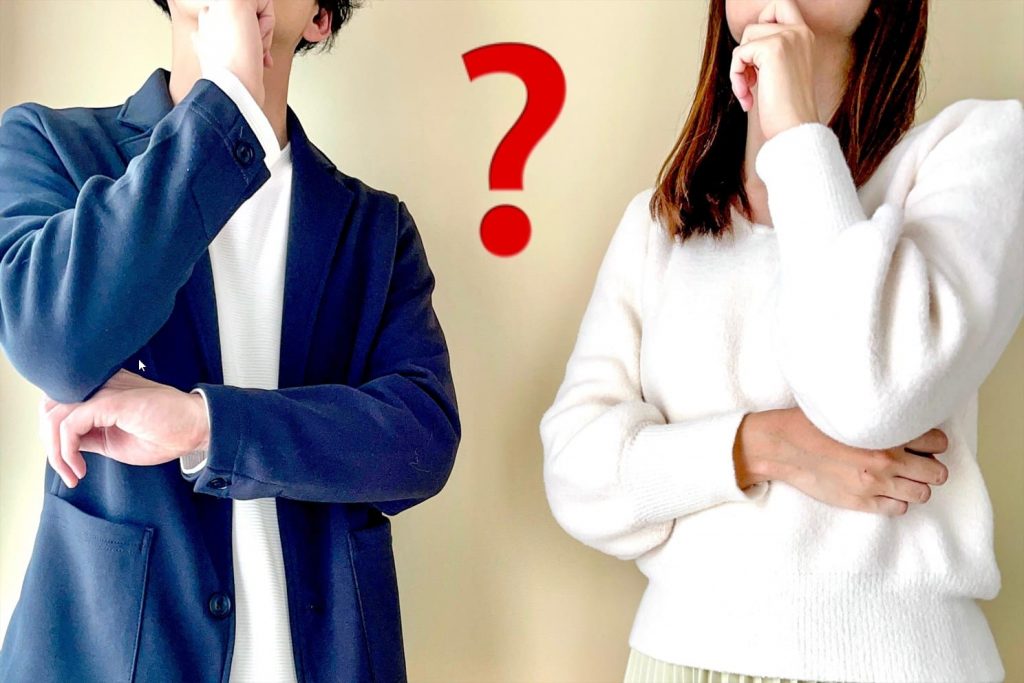
ポリコレ=ポリティカルコレクトネス(Political Correctness)とは、人種や性別をはじめとしたあらゆる差別的な表現をなくそう、とする考え方のことです。頭文字をとって「PC」と略されたり「ポリコレ」と呼ばれたりすることもあります。
差別表現や固定観念からくるステレオタイプな表現を見直し、より多くの人が幸せを感じて過ごせる社会を目指す考え方です。
過去には「政治的な正しさ(妥当性)」といった意味合いで使われていたことがあり、政治的な活動に使われていた言葉です。また現代ではエンタメ作品に様々な影響を与えている側面があり、ファンの間で議論が勃発する場面も見かけます。
このような背景から、ポリティカルコレクトネスがネガティブな意味合いで使われることもあります。
ポリティカルコレクトネスの具体例

ポリティカルコレクトネスという考え方が世の中に浸透したことにより、主に下記の変化がおこりました。
【国内での変化】
- ・職業名の変化
- ・敬称の変化
- ・服装の変化
- ・同性パートナーに関する社会の変化
【海外での変化】
- ・人種表現の変化
- ・宗教に関する表現の変化
詳しく見ていきましょう。
職業名の変化
ポリティカルコレクトネスという概念が浸透することによって、職業名にも変化が発生しています。たとえば男女平等の観点から、下記のような表現の変化がありました。
- ・ビジネスマン→ビジネスパーソン
- ・旦那、妻→パートナー
- ・スチュワーデス→客室乗務員(フライトアテンダント)
- ・看護婦→看護師
- ・カメラマン→フォトグラファー
このように、ポリティカルコレクトネスは職業の名称にも影響を与えているのです。
敬称の変化
ポリティカルコレクトネスの影響によって敬称にも変化が見られます。
たとえば男性は「〇〇くん」、女性は「〇〇ちゃん」という敬称をつけるのが一般的でした。しかし最近では、性別に関係なく「〇〇さん」と呼ぶケースが職場・学校問わず多くなっています。
服装の変化
服装にもポリティカルコレクトネスは大きな影響を与えました。
たとえば学校の場合、これまでは「男性はズボン、女性はスカート」が一般的でした。しかし最近では女性もズボンの制服を選択したり、男性もスカートを選択したりすることが可能な学校も出てきています。
制服だけでなく、水着も男女ともに対応している「ジェンダーレス対応の水着」を導入する学校もあるなど、教育現場にも大きな影響を与えています。
ポリティカルコレクトネスは学校だけでなく、職場の制服にも影響を与えました。男性はスーツ、女性は指定の制服着用を義務にしている企業が過去では一般的でした。しかし最近では、スーツや革靴といった指定をなくして動きやすい服装を選べるようになった企業もあります。
>>ジェンダーレスとは?意味や定義などを徹底解説
>>持続可能な開発目標・SDGsの目標5「ジェンダー平等を実現しよう」のターゲットや現状は?
同性パートナーに関する社会の変化
既存の価値観に当てはまらない、新しい男性と女性の在り方についての動きも日本で見られます。たとえば2023年9月現在、同性婚を巡る訴訟が全国5地裁で行われ「同性婚は違憲かどうか」の判断が地裁によって分かれている状況です。
また一部の企業では「誰でも自分らしく働ける」ようにと、同性パートナーを配偶者に準じた扱いにしたりLGBTQ+に関する啓発活動を行ったりしています。
>>LGBTQ+に関する課題とは?ジェンダー平等に向けた知識や活動を知ろう
人種表現の変化
過去にあった差別的な人種表現の1つに、主にアメリカで黒人のことを「Black」と呼んでいたケースが挙げられます。近年「Black」は差別的・侮蔑的な意図を含んでいる、という理由から呼ばれることが減りました。
最近では黒人のことを「African American」と表現されることが多くなりました。しかし「黒人=アフリカ系」とは必ずしもいえず、アフリカ以外にルーツを持つ黒人にとっては違和感がある表現として現在も問題となっています。
宗教に関する表現の変化
宗教に関する表現にも、ポリティカルコレクトネスは影響を与えています。
たとえば「メリークリスマス」という言葉はキリスト教徒以外の宗教を信仰している人にも配慮するため、海外では「ハッピーホリデー」と呼ばれるようになりました。
ポリティカルコレクトネスが企業で重視される背景

なぜ企業はポリティカルコレクトネスを重視しているのでしょうか。主な背景を3つ解説していきます。
- 企業が多様性を重視しているため
- 海外人材を採用するため
- ハラスメントを予防するため
詳しく見ていきましょう。
企業が多様性を重視しているため
多様性に配慮するため、企業はポリティカルコレクトネスを意識するようになりました。
「ルッキズム」や「LGBTQ+」といった言葉が世間で認知されてきていることから分かるように、多様性が重視される時代になってきています。もし多様性を無視した企業経営をしていると、顧客獲得の機会を逃したり優秀な人を採用しにくくなったりしかねません。
このような背景から、企業はポリティカルコレクトネスをはじめとする、多様性を意識した取り組みにも目を向けるようになったのです。
>>【やめたい】ルッキズムとは?意味やなぜ社会問題なのかを解説
>>LGBTQ+に関する課題とは?ジェンダー平等に向けた知識や活動を知ろう
海外人材を採用するため
海外では日本よりも多様な文化的背景を持つ人が多いです。海外にいる優秀な人材を採用するためにも、企業側はポリティカルコレクトネスを意識して、多様な人材を受け入れられる体制を整えています。
ポリティカルコレクトネスを意識して海外人材も働きやすい環境を整えれば、必要な人材を採用しやすくなったり外国企業との取引がスムーズに進みやすくなったりする、といった効果が期待できます。
ハラスメントを予防するため
ポリティカルコレクトネスの考え方を理解し社内に浸透させることは、ハラスメントの予防にもつながります。
たとえば外国人を採用したりLGBTQ+の人と一緒に働いたりする時、(本人に悪気があるかどうかにかかわらず)相手のことをからかったり否定的な対応をしてしまったりする恐れがあります。
このような扱いは人種差別やハラスメントに当たる可能性があり、企業として問題になりかねません。ポリティカルコレクトネスについて正しく理解すれば、このようなトラブルを予防できるはずです。
ポリティカルコレクトネスに関する企業側の取り組み

ポリティカルコレクトネスに関する企業の取り組みとしては、主に以下のような例が挙げられます。
- ・男女で異なる服装規定を設けない
- ・性別による職種の限定を行わない
- ・性別による給与、福利厚生の格差を設けない
- ・採用面接時に性的指向、宗教、家族に関する質問を行わない
上記のような、性別や性的指向によって差別を行うことは厳禁です。人事・総務部に対応を丸投げすると、個人によって対応にばらつきが発生する恐れがあります。ポリティカルコレクトネスを意識した取り組みを行う場合は、会社が一丸となって取り組む必要があります。
行き過ぎたポリティカルコレクトネスの弊害
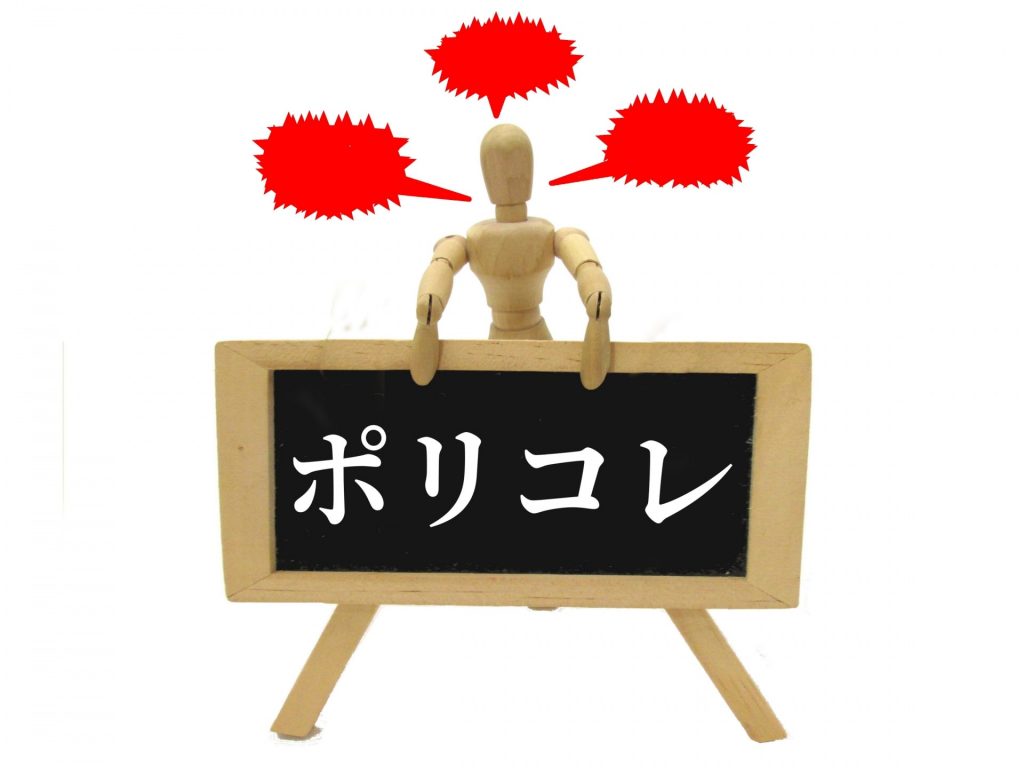
ポリティカルコレクトネスが行き過ぎることによる弊害も発生している点も理解しておきましょう。
たとえば職場でちょっとした言動がハラスメントと捉えられてトラブルに発展する恐れが指摘されています。また映画やアニメ、ゲームといった作品にも影響があり、ファンからは様々な意見が飛び交っています。
職場の息苦しさ
ポリティカルコレクトネスは職場のハラスメント予防にも効果がある一方で、過剰な反応を示す方も一部でいます。
たとえば「髪を切った?」「〇〇ちゃん」と言っただけでセクハラだという人がいます。一方で「この程度でセクハラだと訴えられるのは行き過ぎだ」「職場がなんとなく息苦しくなった」と閉塞感をおぼえる方もいます。
社会的な息苦しさ
行き過ぎたポリティカルコレクトネスは社会全体に、ある種の息苦しさをもたらす恐れがあります。
- ・有名人の女性軽視の発言がSNSで炎上する
- ・美しい女性しか出てこない美容関係の広告が批判される
- ・マイノリティが登場しないエンタメ作品が批判される
上記のような事例は「過剰なポリティカルコレクトネス」として指摘されることがあることです。多様な価値観に配慮した表現を推進することは間違っていませんが、炎上や過剰なクレームなどは行き過ぎではないか、といった意見もあります。
このような事態が続くことで「息苦しい社会になった」と閉塞感をおぼえる人もいます。
映画(アニメ)の設定変更
映画やアニメなど、映像系の作品にもポリティカルコレクトネスをきっかけとした騒動が起こっています。
たとえば原作で「白い肌」や「〇〇色の髪」が特徴として語られているキャラクターが、映画で違う肌の色、髪色の人を起用して物議を醸してしまった作品があります。また原作で設定されていた性別が、映画版では異なる性自認として設定されている作品もあるようです。
このように原作からの不自然な設定変更が原作ファンの間で物議を醸し「違和感をおぼえる」といった指摘が発生するケースもあります。
ゲームキャラクターのジェンダーフリー化
ポリティカルコレクトネスによる影響はゲームにも影響を与えています。
たとえばあるゲームでは、「男性」「女性」といった設定項目をなくし、性別にとらわれず自由な見た目を選択できるようになりました。また「女性らしくない女性」や「男性らしくない男性」が登場するなど、これまでの固定概念にとらわれないキャラクターも登場しています。
こうした動きに「性別に縛られず好きな格好ができる」と肯定的な意見もある一方で、「男らしい(女らしい)登場人物がいないと物足りない」といった趣旨の指摘も散見されます。
ポリティカルコレクトネスに取り組む団体3選
ポリティカルコレクトネスは、社会全体の意識改革だけでなく、さまざまな団体による啓発活動や支援活動にも支えられています。ここでは、特に人権や多様性の尊重に取り組んでいる団体を紹介します。専門家の注目ポイントも参考にしてください。

認定特定非営利活動法人ReBit:LGBTQもありのままで未来を選べる社会を目指して
ReBitは、LGBTQもありのままで未来を選べる社会を目指し、教育・キャリア・福祉・まちづくり事業を展開するLGBTQ分野最大の認定NPO法人です。
代表自身がトランスジェンダーであり、幼少期から性別への違和感を誰にも相談できず、高校時代に自殺未遂を経験しました。「違いを持つ子どもたちも、ありのままで大人になれたら」との願いから、20歳のときに早稲田大学の学生団体としてReBitを設立しました。
団体名には、「少しずつ(Bit)」を「何度でも(Re)」繰り返し、社会を前進させる願いが込められています。2009年より、LGBTQが自分らしく学ぶ・働く・暮らすための環境づくりに取り組んできました。
これまでに、1.8万人を超える困窮や精神的困難を抱えるLGBTQ当事者へのキャリア支援も行ってきました。
ReBitは、LGBTQの支援にとどまらず、多様性が尊重される社会の実現を目指し、教育機関や企業、行政と連携しながら、LGBTQへの理解促進や支援活動を進めています。
- 代表であり創設者の薬師実芳さんは、2015年に「青年版国民栄誉賞」とも称される「人間力大賞」を受賞。ダボス会議の若手リーダーによる国際ネットワーク「グローバル・シェーパーズ」や、オバマ財団の「アジア・パシフィック・リーダー」にも選ばれている
- 2009年に学生団体として早稲田大学で産声を上げ、16年にわたりLGBTQと教育分野に取り組み(2,200回、22万人以上に授業を提供、LGBTQも安心できる学校づくりを支える教職員の育成と伴走も行う)、設立当初からの夢であった「教科書にLGBTQを載せる」ことも教科書会社と連携しながら達成
- 事例集「自治体LGBTQ/SOGIEできることハンドブック」の公開や、中央省庁や200以上の自治体と連携し、LGBTQに関する研修や施策づくりを支援。LGBT理解増進法(2023年6月23日交付・施行)の策定に向けたプロセスにおいて、岸田総理(当時)との意見交換にも参加している
公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本:不合理な差別や暴力に苦しむ人を支援

アムネスティ・インターナショナル日本は、世界中で、人権侵害の実態に関する独自調査、人権教育、キャンペーン、政府などへの提言などに取り組んでいます。
1961年に発足した世界最大の国際人権NGOで、世界200か国で700万人以上が活動に参加しています。国境を越えた自発的な市民運動が評価され、1977年にノーベル平和賞を受賞しました。
不偏不党、独立した立場で活動を行っているため政府からの援助は一切受けずに活動しています。
アムネスティ・インターナショナル日本はすべての人が世界人権宣言にうたわれている人権を享受でき、人間らしく生きることの世界の実現を目指して活動しています。
- 有刺鉄線は「自由を奪われた人びと」を、そして、ろうそくは暗闇を照らす「希望」を表現したロゴマークに込めたメッセージに共感
- 活動資金は、中立性を保つためすべて寄付、会員の会費、活動収入で賄われる
- 寄付の他にも、オンラインアクション(署名)やキャンペーン参加など、「誰か」の絶望を希望にかえる。アクションの紹介が特徴
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら:【実際どう?】アムネスティの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
特定非営利活動法人 Dialogue for People(D4P):無関心を関心に変え、共に社会を動かすメディア型NPO
Dialogue for People(D4P)は、戦争や差別、貧困など、困難な状況に置かれた人々や社会課題の渦中にある地域に足を運び、対話を重ねながら、写真・文章・動画・音楽といった多様な表現で「伝える」活動を行っている団体です。
現場で得た声や視点を丁寧に届けることで、遠い世界の出来事を自分ごととして考え、社会課題の解決につながるきっかけをつくっています。
性的マイノリティの声を可視化する取材や発信も実施。人権や社会課題に関するドキュメンタリーや記事を通じて、多様な生き方への理解を広げる活動を続けています。
「すべての人の基本的人権が守られ、さまざまな違いを超えて多様性が認められる世界」を目指しています。
- 「伝えること」を中核に、社会の無関心に向き合い、無関心を関心に変え、社会に対話の礎を築くことをめざして活動するメディア型NPO。多様な専門性と属性の発信者が、光の当たりにくいテーマにも丁寧に取材・発信し、現場に根差したリアルな声を社会に届けている
- 社会課題と長期的な視点で向き合うために、次世代の「伝える人」の育成にも力を入れている。「育成」と「発信」を両輪に、持続可能な社会づくりに寄与するNPOとしての土台を着実に築いている
- 自らの「足りない部分」や「課題」にも真摯に向き合いながら丁寧な改善を重ねる「等身大の姿勢」が特徴。発信力だけでなく、NPOとしての組織運営にも誠実に取り組み、信頼と持続可能性を築いている
ポリティカルコレクトネスを正しく理解しよう

本記事ではポリティカルコレクトネスについて解説しました。ここで紹介した内容をまとめます。
- ・ポリティカルコレクトネスとは、あらゆる差別をなくすことを目的とした考え方のこと
- ・ポリティカルコレクトネスは表現や服装に大きな影響を与えている
- ・行き過ぎたポリティカルコレクトネスについて疑問視する声もある
ポリティカルコレクトネスは人種や性別による差別・制約から私たちを自由にして、より過ごしやすい社会を実現するために役立つ考え方です。一方で行き過ぎたポリティカルコレクトネスは、かえって不自由な社会を助長しかねないなど、課題も指摘されています。
この機会にポリティカルコレクトネスについて正しく理解し、自分が差別や偏見のあるモノの見方をしていないか、考えてみてはいかがでしょうか。
>>【やめたい】ルッキズムとは?意味やなぜ社会問題なのかを解説
▼ポリティカルコレクトネスに取り組む団体
| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |
|---|---|
| ReBit | ・代表であり創設者の薬師実芳さんは、2015年に「青年版国民栄誉賞」とも称される「人間力大賞」を受賞。ダボス会議の若手リーダーによる国際ネットワーク「グローバル・シェーパーズ」や、オバマ財団の「アジア・パシフィック・リーダー」にも選ばれている ・2009年に学生団体として早稲田大学で産声を上げ、16年にわたりLGBTQと教育分野に取り組み(2,200回、22万人以上に授業を提供、LGBTQも安心できる学校づくりを支える教職員の育成と伴走も行う)、設立当初からの夢であった「教科書にLGBTQを載せる」ことも教科書会社と連携しながら達成 ・事例集「自治体LGBTQ/SOGIEできることハンドブック」の公開や、中央省庁や200以上の自治体と連携し、LGBTQに関する研修や施策づくりを支援。LGBT理解増進法(2023年6月23日交付・施行)の策定に向けたプロセスにおいて、岸田総理(当時)との意見交換にも参加している |
| アムネスティ・インターナショナル日本 | ・有刺鉄線は「自由を奪われた人びと」を、そして、ろうそくは暗闇を照らす「希望」を表現したロゴマークに込めたメッセージに共感 ・活動資金は、中立性を保つためすべて寄付、会員の会費、活動収入で賄われる ・寄付の他にも、オンラインアクション(署名)やキャンペーン参加など、「誰か」の絶望を希望にかえる。アクションの紹介が特徴 |
| Dialogue for People(D4P) | ・「伝えること」を中核に、社会の無関心に向き合い、無関心を関心に変え、社会に対話の礎を築くことをめざして活動するメディア型NPO。多様な専門性と属性の発信者が、光の当たりにくいテーマにも丁寧に取材・発信し、現場に根差したリアルな声を社会に届けている ・社会課題と長期的な視点で向き合うために、次世代の「伝える人」の育成にも力を入れている。「育成」と「発信」を両輪に、持続可能な社会づくりに寄与するNPOとしての土台を着実に築いている ・自らの「足りない部分」や「課題」にも真摯に向き合いながら丁寧な改善を重ねる「等身大の姿勢」が特徴。発信力だけでなく、NPOとしての組織運営にも誠実に取り組み、信頼と持続可能性を築いている |
寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん
NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー
大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。
寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。
国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。