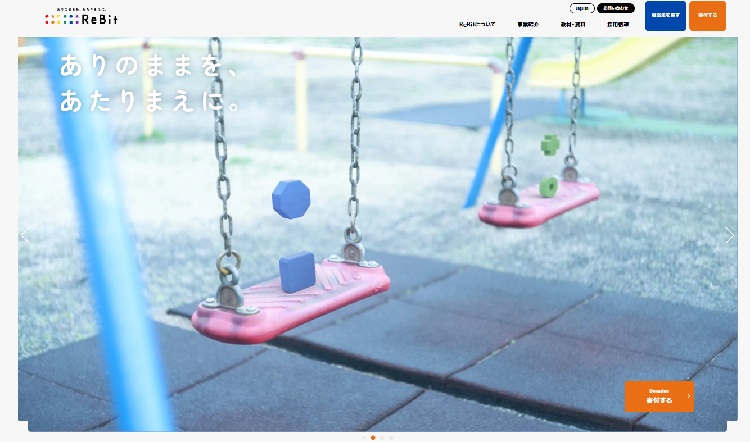LGBTQ+を含む性的マイノリティは世界中にいます。彼らは他者と少し違うことから、不安を抱き、差別的あるいは侮辱的な扱いを受け、ありのままに生きられない社会で生活しなければいけません。
同じ人間である以上、平等に扱われなければいけませんが、様々な分野でまだ課題が残っています。
このような課題に対して日本ではどのような取り組みが行われているのか、この記事で解説します。
LGBTQ+に関する課題とは?ジェンダー平等に向けた知識や活動を知ろう
『紛争・貧困などによって困難に直面する子どもたち』
を無料で支援できます!!
本サイト運営会社のgooddo(株)が応援している『ワールド・ビジョン・ジャパン』の公式LINEを友だち追加すると、「困難に直面する子どもたちのために活動」するワールド・ビジョン・ジャパンに、gooddoから支援金として10円をお届けしています!
支援は簡単。あなたがLINE友だち追加するだけ!一切負担はかかりません。この無料支援にあなたも参加しませんか?
LGBTQ+について理解しよう

LGBTQ+は性的マイノリティ(性的少数者:セクシャルマイノリティ)を表す言葉の1つであり、恋愛対象が誰になるかという性的指向と身体の性と心の性の不一致が起こる性自認に分かれます。
性的指向は女性の同性愛者(レズビアン)、男性の同性愛者(ゲイ)、両性愛者(バイセクシャル)に分かれ、性自認はトランスジェンダーと呼ばれます。 このような性的指向や性自認は多くの場合思春期に認識しますが、現在の日本ではその後の学校生活や社会生活で困難に直面する場面が増えます。
教育や仕事、結婚、医療、公的サービスでさえ様々な問題が起こります。 本来であればLGBTQ+など性的マイノリティであっても差別的な扱いを受けることなく、平等に、かつありのまま生きられる社会でなければいけません。
しかし実際は差別の問題や、通常であれば享受できる権利やサービスを受けられないといった状況が散見されています。 どういった問題が現状起こっているのかは後述しますが、そのケースは様々です。
自分の発言が誰かを傷つけている可能性
LGBTQ+の人々に向けられる、差別的あるいは侮辱的発言は彼らを傷つけます。 差別、または侮辱に当たらないと思った言動であっても、LGBTQ+の人が傷ついている可能性があるのです。
例えば相手から性的マイノリティであることを打ち明けられたとして、驚いたり戸惑ったりすることもあるかもしれません。 しかし、まずは相手の言葉や相談内容に耳を傾けてみましょう。 お互いに相手を尊重し、理解し合うための行動や思いやりが大切です。
他にも本人の許可なく、第三者に性的マイノリティであることを打ち明けられたと伝えるのも、人を傷つけることになります。
このように他人に暴露するのをアウティングといいますが、軽い気持ちや面白半分で他人に暴露すれば、重大な人権侵害にもなります。 性的マイノリティでなくとも、自らの秘密を誰かに暴露されることと同じことです。
自分自身はそう思っていない行為でも、相手にとっては心に傷を負うことになりかねません。 LGBTQ+について深く理解すること、そしてその相手は自分と対等で真摯に向き合うべき相手だと思って接する必要があります。
- LGBTQ+は性的マイノリティ(性的少数者:セクシャルマイノリティ)を表す言葉の1つであり、恋愛対象が誰になるかという性的指向と身体の性と心の性の不一致が起こる性自認に分かれる
- 性的指向や性自認は多くの場合思春期に認識するが、現在の日本では学校生活や社会生活で困難に直面する場面が増える
- LGBTQ+について深く理解すること、そしてその相手は自分と対等で真摯に向き合うべき相手だと思って接する必要がある
下記の本では、日本よりもLGBTQ+に対して理解が進んでいるアメリカが、どのような運動の歴史を歩んできたのか解説しています。
LGBTQ+への理解を深めるヒントが書かれているため、気になる方はぜひチェックしてください。
(出典:法務省人権擁護局「多様な性について考えよう!」)
(出典:参議院「LGBTの現状と課題」,2017)
LGBTQ+を取り巻く様々な問題とは

日本でのLGBTQ+に関する課題はまだまだ山積みであり、解決しなければならないものが多くあります。 先ほども触れたように教育や仕事、結婚など各分野において、直面している困難やそれぞれ改善するための取り組みはなされていますが、世界的に見れば日本の対応や法整備などは遅れているといわざるを得ません。
それではどういった困難や課題、そして現状になっているのか、それぞれの分野ごとに紹介します。
教育・仕事
教育の現場ではLGBTQ+への対応が特に強く求められます。 これはLGBTQ+などの性的マイノリティが、自身がそうであると認識するのが思春期に多いこと、そして性的マイノリティへの周りの理解や、教職員を含む多くの人たちの理解と支援がなければ、問題のない学校生活は送れないためです。
実際に学校でLGBTQ+であることを打ち明けた生徒が、「男(女)のくせに」、「気持ち悪い」などの差別的あるいは侮辱的な言葉を受け、自尊感情を深く傷つけられることも少なくありません。
また本来理解しサポートしなければいけない教員からも、不適切な対応をされた事例もあります。 思春期は人格形成に必要な時期であり、そこで精神的な傷を負えば、その子どもの人生に大きな影響を与える可能性は十分にあります。
仕事においても同様に、LGBTQ+であることを面接中に打ち明けたところ、就活の面接を打ち切られたというケースも報告されています。
あるいは昇格や昇進で結婚要件があったのに、同性パートナーは認められず、昇進・昇格ができなかったということもあったようです。 このように学校あるいは職場の環境において、LGBTQ+への理解が乏しく、また認められていないことによる問題がいくつも発生しているという現状があります。
下記の本では、トランスジェンダーの著者が、どのような環境の職場なら働きやすいのか、わかりやすく解説しています。
カミングアウトされたときにどうしたらいいのか、どのような言葉をかけたら相手を傷付けないのか、自分の身に起こったときの対処方法を知るのにピッタリな1冊ですので、ぜひチェックしてください。

結婚
日本では同性婚やパートナーシップ法などの法整備が行き届いておらず、同性婚および同性パートナーが認められていない状態にあります。 これはG7の中では日本だけであり、先進国の中でも遅れている状態にあることは否めません。同性パートナーでは家族を形成できない状態にあります。
医療
医療の場面においても様々な課題があります。 医療機関ではLGBTQ+への理解が深くなされていなければいけませんが、専門機関も少なく、場合によってはLGBTQ+を認めてもらえないケースもあります。
例えば一緒に暮らしているパートナーが意識不明に陥り入院した際、同性パートナーであったため、病院や医師から安否情報の提供や治療内容の説明を受けられず、面会も拒否された事例があります。
またトランスジェンダーでありながら戸籍上の性別が変更できていない場合、医療機関の受付で戸籍上の名前で呼ばれることから、受診し辛くなったケースもあります。
結婚の問題にも関わりますが、同性パートナーが認められないことや、性的マイノリティへの配慮の欠如が医療関係の場でも起こっています。
公的サービス・社会保障
誰もが享受できる公的サービスや社会保障でもLGBTQ+の人々は困難に直面することがあります。 高齢者向け施設において、男女別に施設運営がされていることから、性別に違和感を抱えていることを施設に伝えても考慮されず、戸籍上の性別で分類され精神的な負担が大きかったという人がいます。
あるいは同性パートナーと公営住宅への入居を申し込もうとしたが、同居親族に当たらないとして拒否されたケースもあります。 法整備がなされていないこと、理解がなされず配慮が欠けていることから、このような問題が散見しています。
- 日本での性的指向に関わる問題の現状はまだまだ課題が山積みであり、解決しなければならないものがたくさんある
- 思春期は人格形成に必要な時期であるため、教育の現場ではLGBTQ+への対応が特に強く求められる
- 日本ではLGBTQ+への理解が乏しく法整備がなされていないこと、理解がなされず配慮が欠けていること、認められていないことによる問題が発生している/li>
(出典:内閣府「世界におけるLGBTの権利」)
(出典:LGBTの現状と課題 (参議院常任委員会調査室・特別調査室,2017))
日本政府のLGBTQ+に関する課題への取り組み

LGBTQ+の各分野への日本の対応は、現代のジェンダー平等を目標とした世界の動きから見れば、大きな遅れがあるといわざるを得ない状況です。 しかし、日本でもこれまで様々な取り組みが行われています。
2003年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」を成立し、翌年施行して以降、様々な対応を行っています。 特に教育関係においては2014年に文部科学省が学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査の公表を実施。
さらに2015年には「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」を発出し、教育現場における取り組みの基準を設けています。
また2016年には文部科学省が教職員向け手引を作成し、公表するなど学校でのLGBTQ+の子どもたちへの支援を徹底しています。 他にも、男女雇用機会均等法に基づく改正セクハラ指針の施行や、いじめ防止対策推進法に基づく基本方針が改定されています。
続いて2020年6月には「パワハラ防止対策関連法(労働施策総合推進法)」が施行され、SOGI*ハラスメント対策として、企業での取り組みも広がってきています。
同時にパートナーシップ制度を導入する自治体も増えてきており、2022年10月には240自治体、人口にして55%以上をカバーするまでに広がっているのです**。
これらは教育だけでなく、仕事などでも適用される内容です。 政党を超えた組織として、LGBTQ+に関する課題を考える国会議員連盟の発足や自民党における「性的指向・性自認に関する特命委員会」の設置も対応の1つといえます。
LGBTQ+を取り巻く問題に対して、いくつもの対応や取り組みはなされていますが、それでも慎重に議論を進めている部分も多く、世界の動きと比べればどうしても遅いという事実があります。
また日本は、現行法の改正・改定などは行われているものの、同性婚をはじめとする決定的な法整備がされていません。 海外では同性婚を認める法律の施行や、結婚に準ずるパートナーシップ法が成立している国も増えていることから、日本の遅れが見られます。
*SOGI:性的指向(sexual orientation)と性自認(gender identity)の頭文字を取った略称
(*出典:厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために)
(**出典:渋谷区・虹色ダイバーシティ 全国パートナーシップ制度共同調査)
LGBT法連合会の取り組み
日本政府の法整備の遅れを受け、性的指向および性自認などにより困難を抱えている当事者の人々に対する法整備のための全国連合会「LGBT法連合会」が2015年に発足されました。
この連合会にはいくつかのNPO・NGOなどが代表団体を務めており、法整備に向けた働きかけを行っています。
主な活動としては性的指向や性自認に関する困難の整理と周知啓発、情報発信、国政に対しての政策提言などです。 また法案としてLGBT差別禁止法の必要性を訴え、これを提案するといった取り組みも行われています。
- 日本は現行法の改正・改定などは行われているが、現代のジェンダー平等を目標とした世界の動きから見れば対応は遅れている
- 2003年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」を成立し、翌年施行して以降、様々な対応を行っている
- 性的指向および性自認などにより困難を抱えている当事者などに対する法整備のための全国連合会「LGBT法連合会」が2015年に発足された
LGBTQを支援するおすすめ団体3選
ここからは、LGBTQの支援を行う団体を紹介します。専門家の注目ポイントも参考にしてください。

認定特定非営利活動法人ReBit:LGBTQもありのままで未来を選べる社会を目指して
ReBitは、LGBTQもありのままで未来を選べる社会を目指し、教育・キャリア・福祉・まちづくり事業を展開するLGBTQ分野最大の認定NPO法人です。
代表自身がトランスジェンダーであり、幼少期から性別への違和感を誰にも相談できず、高校時代に自殺未遂を経験しました。「違いを持つ子どもたちも、ありのままで大人になれたら」との願いから、20歳のときに早稲田大学の学生団体としてReBitを設立しました。
団体名には、「少しずつ(Bit)」を「何度でも(Re)」繰り返し、社会を前進させる願いが込められています。2009年より、LGBTQが自分らしく学ぶ・働く・暮らすための環境づくりに取り組んできました。
これまでに、1.8万人を超える困窮や精神的困難を抱えるLGBTQ当事者へのキャリア支援も行ってきました。
ReBitは、LGBTQの支援にとどまらず、多様性が尊重される社会の実現を目指し、教育機関や企業、行政と連携しながら、LGBTQへの理解促進や支援活動を進めています。
- 代表であり創設者の薬師実芳さんは、2015年に「青年版国民栄誉賞」とも称される「人間力大賞」を受賞。ダボス会議の若手リーダーによる国際ネットワーク「グローバル・シェーパーズ」や、オバマ財団の「アジア・パシフィック・リーダー」にも選ばれている
- 2009年に学生団体として早稲田大学で産声を上げ、16年にわたりLGBTQと教育分野に取り組み(2,200回、22万人以上に授業を提供、LGBTQも安心できる学校づくりを支える教職員の育成と伴走も行う)、設立当初からの夢であった「教科書にLGBTQを載せる」ことも教科書会社と連携しながら達成
- 事例集「自治体LGBTQ/SOGIEできることハンドブック」の公開や、中央省庁や200以上の自治体と連携し、LGBTQに関する研修や施策づくりを支援。LGBT理解増進法(2023年6月23日交付・施行)の策定に向けたプロセスにおいて、岸田総理(当時)との意見交換にも参加している
公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本:不合理な差別や暴力に苦しむ人を支援

アムネスティ・インターナショナル日本は、世界中で、人権侵害の実態に関する独自調査、人権教育、キャンペーン、政府などへの提言などに取り組んでいます。
1961年に発足した世界最大の国際人権NGOで、世界200か国で700万人以上が活動に参加しています。国境を越えた自発的な市民運動が評価され、1977年にノーベル平和賞を受賞しました。
不偏不党、独立した立場で活動を行っているため政府からの援助は一切受けずに活動しています。
アムネスティ・インターナショナル日本はすべての人が世界人権宣言にうたわれている人権を享受でき、人間らしく生きることの世界の実現を目指して活動しています。
- 有刺鉄線は「自由を奪われた人びと」を、そして、ろうそくは暗闇を照らす「希望」を表現したロゴマークに込めたメッセージに共感
- 活動資金は、中立性を保つためすべて寄付、会員の会費、活動収入で賄われる
- 寄付の他にも、オンラインアクション(署名)やキャンペーン参加など、「誰か」の絶望を希望にかえる。アクションの紹介が特徴
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら:【実際どう?】アムネスティの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
特定非営利活動法人 Dialogue for People(D4P):無関心を関心に変え、共に社会を動かすメディア型NPO
Dialogue for People(D4P)は、戦争や差別、貧困など、困難な状況に置かれた人々や社会課題の渦中にある地域に足を運び、対話を重ねながら、写真・文章・動画・音楽といった多様な表現で「伝える」活動を行っている団体です。
現場で得た声や視点を丁寧に届けることで、遠い世界の出来事を自分ごととして考え、社会課題の解決につながるきっかけをつくっています。
性的マイノリティの声を可視化する取材や発信も実施。人権や社会課題に関するドキュメンタリーや記事を通じて、多様な生き方への理解を広げる活動を続けています。
「すべての人の基本的人権が守られ、さまざまな違いを超えて多様性が認められる世界」を目指しています。
- 「伝えること」を中核に、社会の無関心に向き合い、無関心を関心に変え、社会に対話の礎を築くことをめざして活動するメディア型NPO。多様な専門性と属性の発信者が、光の当たりにくいテーマにも丁寧に取材・発信し、現場に根差したリアルな声を社会に届けている
- 社会課題と長期的な視点で向き合うために、次世代の「伝える人」の育成にも力を入れている。「育成」と「発信」を両輪に、持続可能な社会づくりに寄与するNPOとしての土台を着実に築いている
- 自らの「足りない部分」や「課題」にも真摯に向き合いながら丁寧な改善を重ねる「等身大の姿勢」が特徴。発信力だけでなく、NPOとしての組織運営にも誠実に取り組み、信頼と持続可能性を築いている
LGBTQ+に関する課題の解決とジェンダー平等のために私たちができること

日本では、LGBTQ+の人々への対応や法整備などが世界的に見ても遅れていると言えます。しかし、LGBTQ+に関する課題の解決やジェンダー平等に向けて活動する人々や団体はたくさんあります。
LGBTQ+の人々を取り巻く様々な課題をより早く解決するために、LGBTQ+差別問題に取り組んでいる人々や団体がいますが、継続して活動するための資金や人材がまだまだ足りていません。
そこで、無理のない範囲であなたのお力を貸していただけませんか?
お願いしたいのは、選択肢から選ぶだけの3つの質問にお答えいただくだけです。
お金はもちろん、個人情報や何かの登録も一切不要で、30秒あれば終わります。
それだけで、LGBTQ+差別の撲滅をめざす活動をしている方々・団体に本サイトの運営会社であるgooddo(株)から支援金として10円をお届けします。
お手数おかけしますが、お力添えいただけますようお願いいたします。
『紛争・貧困などによって困難に直面する子どもたち』
を無料で支援できます!!
本サイト運営会社のgooddo(株)が応援している『ワールド・ビジョン・ジャパン』の公式LINEを友だち追加すると、「困難に直面する子どもたちのために活動」するワールド・ビジョン・ジャパンに、gooddoから支援金として10円をお届けしています!
支援は簡単。あなたがLINE友だち追加するだけ!一切負担はかかりません。この無料支援にあなたも参加しませんか?
▼LGBTQを支援するおすすめ団体
| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |
|---|---|
| ReBit | ・代表であり創設者の薬師実芳さんは、2015年に「青年版国民栄誉賞」とも称される「人間力大賞」を受賞。ダボス会議の若手リーダーによる国際ネットワーク「グローバル・シェーパーズ」や、オバマ財団の「アジア・パシフィック・リーダー」にも選ばれている ・2009年に学生団体として早稲田大学で産声を上げ、16年にわたりLGBTQと教育分野に取り組み(2,200回、22万人以上に授業を提供、LGBTQも安心できる学校づくりを支える教職員の育成と伴走も行う)、設立当初からの夢であった「教科書にLGBTQを載せる」ことも教科書会社と連携しながら達成 ・事例集「自治体LGBTQ/SOGIEできることハンドブック」の公開や、中央省庁や200以上の自治体と連携し、LGBTQに関する研修や施策づくりを支援。LGBT理解増進法(2023年6月23日交付・施行)の策定に向けたプロセスにおいて、岸田総理(当時)との意見交換にも参加している |
| アムネスティ・インターナショナル日本 | ・有刺鉄線は「自由を奪われた人びと」を、そして、ろうそくは暗闇を照らす「希望」を表現したロゴマークに込めたメッセージに共感 ・活動資金は、中立性を保つためすべて寄付、会員の会費、活動収入で賄われる ・寄付の他にも、オンラインアクション(署名)やキャンペーン参加など、「誰か」の絶望を希望にかえる。アクションの紹介が特徴 |
| Dialogue for People(D4P) | ・「伝えること」を中核に、社会の無関心に向き合い、無関心を関心に変え、社会に対話の礎を築くことをめざして活動するメディア型NPO。多様な専門性と属性の発信者が、光の当たりにくいテーマにも丁寧に取材・発信し、現場に根差したリアルな声を社会に届けている ・社会課題と長期的な視点で向き合うために、次世代の「伝える人」の育成にも力を入れている。「育成」と「発信」を両輪に、持続可能な社会づくりに寄与するNPOとしての土台を着実に築いている ・自らの「足りない部分」や「課題」にも真摯に向き合いながら丁寧な改善を重ねる「等身大の姿勢」が特徴。発信力だけでなく、NPOとしての組織運営にも誠実に取り組み、信頼と持続可能性を築いている |
寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん
NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー
大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。
寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。
国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。