「ホームレスを支援する団体に寄付をしたい」
「寄付以外の形でも協力したい」
このように考える方のために、本記事では以下の内容を解説します。
- ・ホームレス支援におすすめの寄付先
- ・信頼できる団体の選び方
- ・寄付以外の支援方法
- ・日本のホームレスの現状
信頼できる寄付先を見極めるには、活動実績や寄付の使い道、公的認証の有無を調べるのがおすすめです。
寄付以外の活動として、ボランティアやフードドライブへの参加が考えられます。また、日本のホームレスの現状を知ることで、より効果的な支援ができるかもしれません。
信頼できる寄付先の選び方を参考に、ホームレスを支援する活動に参加してみませんか?
ホームレス支援におすすめの寄付先5選

住まいを失い、困窮するホームレスの人々を支援する取り組みは、一人ひとりの寄付によって支えられています。実際に支援活動を行っているおすすめの寄付先を5つ紹介します。NPOの専門家やgooddoマガジン編集部による注目ポイントも参考にしてください。

【寄付先1】認定NPO法人抱樸(ほうぼく):「誰ひとり取り残さない社会」を目指す実践型支援団体
認定NPO法人抱樸は、北九州市を拠点に、ホームレス状態や生活困窮にある人々の支援を行う団体として30年以上の歴史を持ちます。
「誰ひとり取り残さない社会」を目指し、住まい・仕事・福祉・教育・地域とのつながりなど、複合的な課題に向き合いながら包括的な支援を展開しています。
特に注目されるのが、地域で支え合う仕組みを形にした「希望のまちプロジェクト」。生活困窮者や高齢者、障がいのある人などが安心して暮らせるコミュニティを創出し、孤立ゼロ社会の実現を目指しています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- 1988年から37年の活動実績
- 創造的に事業を興し必要に応じて連携の仕組みを創り、問題解決型の支援に加え、たとえ解決できなくても「つながり続ける」ことを大事にする「伴走型支援」が特徴
- コロナ禍で仕事と住まいを失う人を支えるために行ったクラウドファンディングで1億円を超える支援実績
【寄付先2】認定NPO法人Homedoor:アイデアでホームレス問題に取り組む

ホームレス問題と違法駐輪問題を同時に解決する、シェアサイクル事業HUBchariを中心に、路上からでも働ける仕事づくりに注力しています。
「ホームレス状態を生み出さない日本の社会構造をつくる」をビジョンに2010年から活動に取り組んでいます。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- ホームレス状態から抜け出したいと思っても抜け出せない状況や、偏見がなくならない状況を、「6つのチャレンジ」で解決する一連の支援活動が特徴
- 1日30円から始められるサポーター制度があり、寄付金でできることのわかりやすい紹介
- 年次報告書が工夫され、寄付の使途や活動の成果がわかりやすく紹介
【寄付先3】認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパン:日本初のフードバンク

様々な理由で廃棄される食品を引き取り、それらを児童養護施設、DV被害者のためのシェルター、ホームレス、こども食堂などに届ける活動を行っています。
日本でのフードセーフティネットの構築を目的にしています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- 日本初のフードバンク。コロナ禍の影響を受け、例年以上の食の支援を必要とする利用者増が見込まれ、団体への期待は大きい
- お金や時間の寄付の他に、食べ物の寄付がある
- 食品ロスの問題提起、ハローキティSDGs応援などわかりやすい動画での紹介
【寄付先4】認定NPO法人ビッグイシュー基金:路上脱出ガイドが特徴的

『路上脱出ガイド』の配布、健康・住居等の相談業務を軸に多面的にホームレス問題に取り組んでいます。
貧困問題の解決と「誰にでも居場所と出番のある包摂社会」の形成に向けて活動を続けています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- 「誰もが居場所と出番のある社会の実現に向けてあなたの力をお貸しください」「応援をいただいて挑戦したいこと」のお願い
- 寄付だけでなく、ボランティア、会員、物品寄付など、活動へのさまざまな応援・参加の方法が紹介されている
- 「知る・広める」の応援方法があり、詳細なイベント情報の掲載、パンフレットや年次報告書などの資料を読むことができる
【寄付先5】公益社団法人 ホームレス支援全国ネットワーク:いのちを守り、自立を支える仕組みを全国に
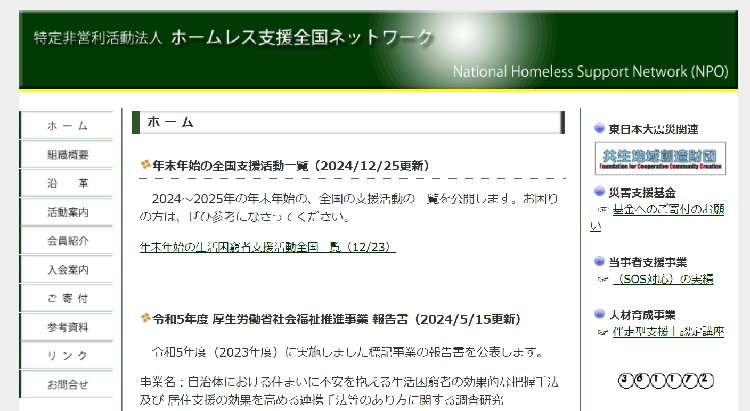
ホームレス支援全国ネットワークは、2007年に全国のホームレス・生活困窮者支援団体が連携して発足したネットワーク組織です。地域の事情や歴史的背景に根ざした支援活動を尊重しつつ、共通の課題に対しては団体同士が協力し合い、より包括的な支援体制を築いています。
「路上からの脱出」だけでなく、自立後の継続的な支援や、ホームレス状態に陥らないための予防支援、多様な自立の形を模索しながら、「いのちを大切にする社会」の実現を目指しています。
gooddoマガジン編集部の注目ポイント3つ!
- 「ホームレス自立支援法」や福祉制度を活用しながらも、制度のはざまにいる人々にも寄り添う支援を実施
- 就労支援にとどまらず、住まい・福祉・心のケアまで含めた“全人的”な自立支援に取り組んでいる
- 地域間での情報共有や協働体制を重視し、多様な団体が互いに補完し合えるネットワークづくりを推進
ホームレス支援団体に寄付する前に確認!信頼できる団体の選び方

ホームレス支援団体に寄付をしたいと考えたとき、どの団体を選ぶべきなのでしょうか。見極めるための重要ポイントは以下の通りです。
- ・活動実績を確認する
- ・寄付の使い道を確認する
- ・認定NPO法人の資格や表彰実績を確認する
信頼できる団体選びの3つのポイントを紹介します。
活動実績を確認する
ホームレス支援団体を選ぶ際には、その団体の活動実績を丁寧に確認することが大切です。具体的な支援人数や実施プログラムの成果など、数値化された実績が公開されているかを見るとよいでしょう。
また、団体のホームページやSNSで日々の活動内容を確認することで、継続的な支援を行っているかどうかを判断できます。長期にわたって着実に活動を続け、成果を上げている団体は信頼性が高いと言えます。
寄付の使い道を確認する
寄付の使い道を確認することも重要です。団体の公式サイトで活動報告書や決算書が公開されているか、寄付金や物品の活用方法が具体的に明記されているかを確認しましょう。
透明性の高い団体は、プロジェクトの内容や活動費の内訳、会計報告書などを積極的に開示しています。寄付者の意図に沿った形で資金が活用されているかを事前に調べることで、安心して支援を託すことができます。
認定NPO法人の資格や表彰実績を確認する
その団体が認定NPO法人の資格を有しているか、または国や地方自治体からの表彰実績があるかをチェックしましょう。
認定NPO法人の認定を受けるには、公益性・信頼性の高い運営体制や情報公開が求められ、一定の厳しい基準を満たす必要があります。また、行政機関などからの表彰は、活動の成果や社会的な評価を示すものとして、信頼性を判断する一つの材料となります。
公式ウェブサイトや情報公開資料で、認定状況や表彰の内容・受賞歴を確認することで、安心して支援できる団体かどうかを見極めることができます。
ホームレス支援のために寄付以外でできること
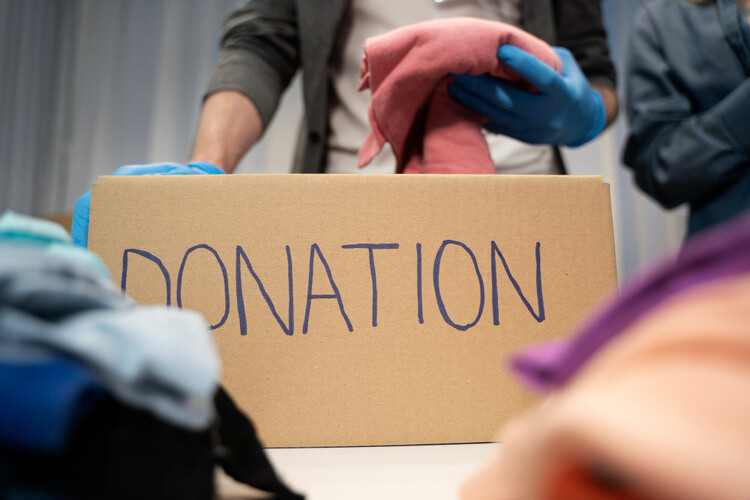
ホームレスを支援する方法は、寄付以外にもあります。主な支援は以下の3つです。
- ・ボランティア活動に参加する
- ・物品を寄付する
- ・フードドライブに参加する
ここでは、金銭的な寄付以外の方法について、詳しく解説します。
ボランティア活動に参加する
ホームレス支援には、金銭的な寄付だけでなく、ボランティア活動に参加する方法もあります。
例えば、炊き出しでは温かい食事を提供し、パトロール活動では定期的に生活場所を訪れ、食料の配布や相談を行います。衣類や生活用品の配布は炊き出しと併せて実施されることも多く、日常生活を支える重要な支援の一環となっています。
また、ホームレスの方々が自立できるよう、就労支援や住居支援、生活相談といった長期的なサポートも不可欠です。
これらの活動は、単独のNPOだけでなく、行政機関と連携して実施することで、より効果的な支援となります。
炊き出しボランティアについては、以下の記事でも解説しています。
>>炊き出しボランティアとは?参加する方法や支援団体も紹介
物品を寄付する
ホームレス支援団体には、金銭的な寄付以外にも実用的な物品を寄付することができます。衣類であれば新品の靴下や下着など、食品であればレトルト食品やインスタントコーヒーなどの保存食を受け付けていることが多いです。また冬季には使い捨てカイロなどを募集している団体もあります。
また、使用済みの衣類よりも、テレフォンカードや商品券などの金券類が実用的な支援になることもあります。寄付する前に各団体の公式サイトで必要としている物品を確認するとよいでしょう。
フードドライブに参加する
フードドライブも、ホームレスへの効果的な支援方法の一つです。地域の集会所や学校などで定期的に開催され、参加者は家庭で余っている缶詰や乾麺、レトルト食品などを持ち寄ります。
賞味期限が一ヶ月以上残っている未開封の食品であれば誰でも気軽に寄付できるのが特徴です。また、フードドライブのボランティアとして食品の仕分けや配布を手伝うこともできます。
フードドライブについては、以下の記事をご一読ください。
>>フードドライブとは?実施・参加の手順、寄付におすすめのNPOを紹介【専門メディア】
日本のホームレス問題の現状

ホームレスを支援する活動に取り組む前に、日本のホームレス問題の現状を知る必要があります。ここでは、以下のポイントを解説します。
- ・全国のホームレスの数
- ・ホームレス状態に陥る原因
- ・ホームレス状態からの社会復帰は困難
詳しく見てみましょう。
全国のホームレスの数
厚生労働省の「ホームレスの実態に関する全国調査」(令和6年1月実施)によると、全国で確認されたホームレスの総数は2,820人となっています。その内訳は男性が2,575人、女性が172人、性別不明が73人です。
この数字は年々減少傾向にありますが、統計の数字に表れない「見えないホームレス」の存在も指摘されています。特に、インターネットカフェなどを寝泊まりの場として利用している、いわゆる「ネットカフェ難民」と呼ばれる人々は、公式な統計には反映されにくい傾向があります。
ホームレスとして数に上がっているのは、主に都市公園、河川敷、道路、駅舎などで生活している人々が大半です。
見えにくい女性のホームレスや若者のホームレスについては、以下の記事をご一読ください。
女性のホームレスはなぜ少ない?原因や私たちにできることを解説
>>日本の若者ホームレスとは?実態や原因について解説
ホームレス状態に陥る原因
日本でホームレス状態に陥る原因は性別によって傾向が異なります。
男性の場合は、仕事の減少や倒産、失業といった経済的要因が主な理由となっています。また、職場での人間関係のトラブルや病気、ケガ、高齢化による就労困難も大きな要因です。
一方、女性の場合は家庭関係の悪化や家族との離別・死別などの家族的要因が中心となっています。
このように、男性は仕事関連の問題が、女性は家庭環境の変化が大きく影響しています。
ホームレスが生まれる原因についは、以下の記事をご一読ください。
>>なぜホームレス状態の人が生まれるの?その原因、対策方法とは?
ホームレス状態からの社会復帰は困難
日本ではホームレス状態からの社会復帰が複数の要因により非常に困難な状況にあります。その一つの要因は住所不定であることです。就職活動に必要な履歴書の住所記入や連絡先の提示ができず、安定した仕事に就くことが極めて難しくなっています。
また、住居確保においても大きな障壁があるのが実情です。保証人や初期費用の問題、健康状態の悪化や社会的孤立など個別の課題を抱えている場合も少なくありません。
これらの複合的な障壁により、多くのホームレスが自力での社会復帰を果たせずにいます。
そのため、一人ひとりの状況に応じた継続的な支援体制を整備することが、社会全体の課題として求められています。
ホームレスに関するQ&A

ホームレスに関するよくある質問として、以下の2つを取り上げます。
質問とその回答を見てみましょう。
- ・ホームレスが生活保護を受けない理由は?
- ・ホームレスの自立支援にはどのようなものがある?
ホームレスが生活保護を受けない理由は?
ホームレスの人たちが生活保護を受けていない理由で最も多かったのは、「利用したくない」という気持ちで、男性は約半数(48.9%)、女性は約4割(40.7%)がこう答えています。
また、女性の場合は「自分は利用できないと思っている」人が18.5%もいました。さらに、制度のことを全く知らない女性もいることがわかりました。
出典:厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)の分析結果」
つまり、生活保護を受けられるのに、受けたくないという気持ちから利用を避けたり、制度についての誤解や情報不足があったりして、必要な支援を受けていない人が多いようです。
この結果から、制度の説明をもっと丁寧に行う必要があると言えます。
ホームレスになる原因と生活保護の問題点については、以下の記事をご確認ください。
>>ホームレス状態の人がなくならない原因とは?生活保護の問題点や支援方法について
ホームレスの自立支援にはどんなものがある?
ホームレスの自立支援は多角的なアプローチで行われてきました。就業機会の確保として、求人開拓や職業相談、技能講習などを実施。
また、安定した居住の場を得るため、公営住宅への優先入居や低家賃の民間賃貸住宅の情報提供、住居確保給付金の支給なども行われています。
健康面では保健所による健康相談が、生活面では福祉事務所を中心とした相談・指導体制が確立されています。
自立支援センターでは健康診断や就労支援が実施され、個々の状況に応じた支援が行われるとともに、必要に応じて生活保護も適用されています。
ホームレスの支援や生活保護については、以下の記事でも解説しています。
>>ホームレス状態の人のための支援とは?取り組みや生活保護について知ろう
寄付でホームレス支援を始めよう!

本記事では、以下の内容をお伝えしました。
- ・支援団体への寄付を通してホームレスに支援できる
- ・金銭の寄付以外にも、ボランティアや物品の寄付、フードドライブへの参加などで支援に参加できる
- ・ホームレスの自立には住居提供や就労支援などの包括的な支援が必要
ホームレスの支援活動には、国や地方自治体、NPOなどの公的機関や民間団体が取り組んでいます。こうした団体に寄付をしたり、ボランティアとして関わったりすることで、誰でも支援に参加することが可能です。
今回の記事をきっかけに、できる範囲でホームレス支援を始めてみてはいかがでしょうか。
▼ホームレス支援におすすめの団体
| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |
|---|---|
| 抱樸(ほうぼく) |
・1988年から37年の活動実績 ・創造的に事業を興し必要に応じて連携の仕組みを創り、問題解決型の支援に加え、たとえ解決できなくても「つながり続ける」ことを大事にする「伴走型支援」が特徴 ・コロナ禍で仕事と住まいを失う人を支えるために行ったクラウドファンディングで1億円を超える支援実績 |
寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー
大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。
寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。
大阪マラソンチャリティ事務局担当や、国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。


