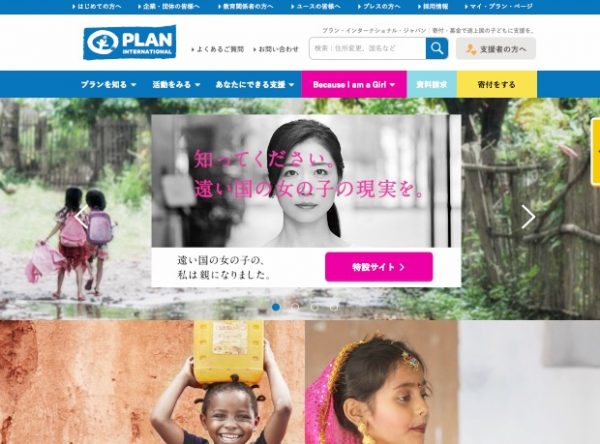貧困や紛争などの問題や、自然災害。
これらが原因となって起こる社会問題が、「自分の人生」を生きたい子どもたちの将来への希望をなくしています。
そんな子どもたちの力になりたい、と「寄付をする」ことを検討したとき、
・海外の子どもの支援はどのような団体がしているのか
・それぞれどういった活動をしているのか
・寄付先が信頼できるか不安
と思うことはありませんか?
そこでこの記事では、さまざまなNPOに詳しい寄付アドバイザー河合氏の監修のもと「海外の子どもの支援活動に寄付したい人」のために寄付先の選び方をガイドしていきます。
具体的には
- そもそもどうやって寄付先を選べばいいのか
- 選び方に合わせたおすすめの寄付先一覧と概要
- よくある質問
の順番にお伝えします。
※寄付アドバイザー河合さんのプロフィールは文末に掲載しております。
>>今すぐにおススメの寄付先団体を知りたい方はこちらをクリック
- 1 【海外の子ども支援】寄付先のNPO団体の選び方
- 2 【寄付するなら?】海外の子どもたちを支援するNPO団体を課題別にご紹介!
- 3 寄付しようか迷っている方へ、よくある4つの疑問を解説!
- 4 海外の子どもたちを支援するため、寄付をしよう
【海外の子ども支援】寄付先のNPO団体の選び方
はじめまして。寄付アドバイザーの河合です。
みなさんの寄付先選びをサポートしていきますね。
これから寄付を始める人のために、おすすめしたい3つの選び方を解説します。
おすすめする団体の選び方3つ
- 信頼できるところに寄付する
- 自分が問題だと思うことに取り組む団体に寄付する
- 寄付の使い道がわかりやすいところに寄付する
まずはこの中で自分がしっくりくるものをひとつ選んでみてくださいね。
もちろん、選び方に該当しない団体を否定する訳ではありません。あくまで選び方の一例としてご覧いただければ幸いです。
そして、その次。
それぞれの選び方に応じた見るべきポイントの一例は以下のような感じになります。
選び方1:信頼できるところに寄付したい場合、見るべきポイント(一例)
- 法人格があり3年以上運営している
- 活動の規模が1000万円を超えている
- 個人の寄付を募っていたり、企業と連携している
選び方2:自分が問題だと思うことに取り組む団体に寄付したい場合、見るべきポイント(一例)
- 活動内容に特徴があり、誰も気づいていなかった問題に挑戦している
- 活動を通して、実績と成果を上げている
選び方3:寄付の使い道がわかりやすいところに寄付したい場合、見るべきポイント(一例)
- 活動の詳細や使途がホームページ等に公開されている
- SNSやメルマガ、ブログなどを活用して情報発信している
寄付者にとって必要な情報がわかりやすく発信されていれば、安心して寄付を託すことができます。
特に資金的な情報開示と定期的な活動レポートの更新はポイントではないでしょうか。
こうした選び方と見るべきポイントを参考に、あなたが応援してみたいと思える団体を探してみてくださいね。
【寄付するなら?】海外の子どもたちを支援するNPO団体を課題別にご紹介!

ここからは上記で紹介した3つの選び方の視点で、課題別におすすめの寄付先を紹介していきます。
ぜひあなたのお気に入りの活動を探してみてくださいね。
寄付アドバイザーの河合さんのおすすめポイントも紹介します!
>>貧困で苦しむ子どもが健やかに暮らせるように支援する活動
>>子ども兵や児童労働から守るための支援活動
>>教育を受ける機会がない子どもに教育を届ける活動
【人身売買・人身取引】子どもが売られない社会を目指す支援団体
健康に生きることができて初めて「自分の人生」を生きる一歩を踏み出すことができます。子どもたちへの医療提供や保健教育などの活動をしている団体をご紹介します。
公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン:世界70か国で女の子や女性を支援
世界70カ国以上で、女の子や女性への支援などを行う国際NGOです。
「地域の自立」を最終目標に、教育、子どもの健やかな成長、若者の生計向上支援、性と生殖に関する健康と権利などの分野で活動しています。
プラン・インターナショナルは、ブルキナファソで「女の子が売られない社会づくり」プロジェクトを実施。人身取引被害者の保護や職業訓練を通じた自立支援を行っています。
また、ネパールの国境地域では啓発活動を支援し、「リソースセンター」の開設を通じて人身取引防止の取り組みを強化しています。
「子どもの権利を推進し、貧困や差別のない社会」を実現するために活動しています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- 「教育」「医療」といったピンポイントの“点”のプロジェクトではなく、ジェンダーに配慮しながらあらゆる分野にある課題を特定の村や地域で総合的に解決する“面”の支援。女の子に焦点を当て、支援効果を意識した特徴あるプログラム
- プラン・スポンサーシップ(継続支援)をはじめ、多様な支援メニュー
- 活動の報告を聞くことができる「プラン・ラウンジ」や支援者インタビュー、支援者の声などを参考にすることができる。著名人の支援者もいる
関連記事
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら:【実際どう?】国際NGOプラン・インターナショナルの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
【健康】海外の子どもたちが健康な生活を過ごすための支援団体
健康に生きることができて初めて「自分の人生」を生きる一歩を踏み出すことができます。子どもたちへの医療提供や保健教育などの活動をしている団体をご紹介します。
公益財団法人 日本ユニセフ協会:知名度の高さが信頼に
190の国と地域で子どものために活動するユニセフ(国連児童基金)の日本における国内委員会。
日本国内でユニセフ募金・広報・アドボカシー(政策提言)活動を行っています。
ユニセフの活動を通して「世界中の子どもたちの命と健康が守られる世界」を目指しています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- 国連機関ならではのスケールの大きな質の高い支援ができる。2019年のワクチンの供給数は24億回
- マンスリーサポート(月2,000円など、寄付額は任意)でできることが具体的に示され、支援の成果の報告が充実
- 著名人(親善大使を担う人もいる)、企業・団体などユニセフの多くの支援者の存在
認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン:子どもと繋がりを感じられる
約100カ国で開発援助や緊急人道支援を通して、困難な状況で生きる子どもたちのために活動しています。
活動を通して「すべての子どもたちが健やかに成長できる世界」を目指しています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- 途上国の子どもと心のつながりを持ちながら、支援の成果を感じられる寄付プログラム「チャイルド・スポンサーシップ」が特徴
- 「1日あたり150円の支援で、子どもたちの未来が変わります」「何もかもはできなくとも、何かはきっとできる」などのメッセージから団体が大切にしていることが伝わる
- 「10秒に一人/1日に3つの学校にきれいな水を届ける」「貧困の根本原因を解決することで2億人以上の子どもたちの生活状況が改善」「極度の栄養不良にあった子どもたちの89%が完全に改善」など、活動の影響を具体的な数字で示している
【子ども兵や強制労働】海外の子どもたちが「子ども兵」になることや児童労働から守るための支援団体
子どもから教育を受ける機会を奪い、子どもを危険な環境に置く児童労働や子ども兵の問題。
児童労働が起きない仕組みづくり、児童労働や子ども兵の被害者が職を得られるように教育機会の提供や社会復帰支援などの活動をしている団体を紹介します。
認定NPO法人テラ・ルネッサンス:丁寧なコミュニケーションが特徴
テラ・ルネッサンスは、地雷、小型武器、子ども兵、平和教育という4つの課題に対して、海外の現場での活動、国内での啓発・提言活動を行っています。
また、児童労働の撤廃を目指し、CL-Net(児童労働ネットワーク)に参加し、毎年6月に「レッドカードアクション」を実施。ILOが推進する世界的なキャンペーンで、児童労働の問題を広め、解決の必要性を訴える取り組みを行っています。
元子ども兵の支援においては、自尊心の回復をサポートする心のケア、さらに基礎教育、職業訓練・収入向上支援を実施。支援後に自尊心が1.7倍に、子どもと周りのひとのつながりが3倍以上に、平均収入が50倍以上になるという成果を生み、子どもたちを自立に導いています。
また、18年の歴史を持つテラ・ルネッサンスは京都府から認定NPO法人の認証を受けています。
活動を通して、「すべての生命が安心して生活できる社会」の実現を目指しています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- アフリカのコンゴ、ウガンダ、ブルンジ、アジアのカンボジア、ラオスで「地雷、小型武器、子ども兵」の課題解決に取り組む。こうした課題や自立に向けた取組みに特徴がある
- 日本国内では、岩手県大槌町で東日本大震災復興支援活動「大槌復興刺し子プロジェクト」を2011年から実施。昔から日本に伝わる手仕事の一つである「刺し子」の商品企画・販売を通して、地元人材の雇用や作り手の皆さんの生きがい創出をめざす
- 創設者・理事・事務局長の鬼丸昌也さんの2019年度年次報告書のコメントや「一人ひとりは微力であっても、決して無力ではない」のメッセージが印象的
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら:【実際どう?】テラ・ルネッサンスの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
【教育】海外の子どもたちに、良質な教育を届けるための支援団体
貧困のスパイラルを抜け出すのに重要なのは教育。子どもたちに教育の機会を届ける活動をしている団体を紹介します。
認定NPO法人e-Education:途上国の教育格差を壊すオンライン教育
途上国の地方にいる教育機会に恵まれない子どもに映像教育を届けています。14ヶ国3万人の中高生に教育を届けてきました。
「すべての子どもたちが当たり前のように教育を受けられるような社会」の実現を目指しています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- バングラデシュの教師不足の課題に、日本の予備校モデルを応用した遠隔型教育を10年以上前に開拓
- 若者3人が立ち上げ、多様な経験・経歴のスタッフが参画、100人のチームの規模、1,000人以上のマンスリーサポーターにまで発展
- 環境の変化に合わせて「最高の教育」を提供する方法を進化させながら、設立から10年で3万人以上の子どもに教育を届ける。受賞歴も多い
このように考えている方は、この機会に遺贈寄付を考えてみませんか?
生前に手続きを済ませるだけで、自分の遺産を支援団体に寄付(遺贈寄付)できます。
遺贈寄付先の選び方をチェックする
寄付しようか迷っている方へ、よくある4つの疑問を解説!

1.支援した子どもとコミュニケーションはとれる?
支援団体によっては、子どものプロフィールを見たり手紙でやりとりできたりするところもあります。成長記録や写真を届けてくれる団体も。
また、支援地訪問ツアーや個人訪問などで、寄付先の子どもたちに直接会うことができる場合もあります。
2.寄付先の団体が活動しているか、実態をチェックしたい
集まった募金額や活動内容を公開しているNPOは多くあります。年次報告書や収支報告書をホームページでチェックすることができます。また、ブログやSNSでの日々の活動報告にも目を通してみてください。具体的な活動内容や、お金の使われ方を詳しく知ることができます。
信頼できる寄付先を探すなら、活動内容を公開している寄付先がおすすめです。
3.支援する国や地域は選べるのか?
寄付先のNPOによります。
団体の活動全体への寄付のみ受け付けている団体もありますが、事業地別、プロジェクト別の寄付方法を設けている団体も多くあります。
自分が具体的に支援したい人たちのために寄付が使われるのは嬉しいものですが、団体が一番有効に使えると考える事業や地域に使ってもらえるよう、一任するという考えも支援を効果的に行える方法です。
4.寄付は途中で辞めても大丈夫?
寄付を途中で辞めても問題ありません。
団体のホームページなどの案内に沿って手続きをすることができます。クレジットカード払いなどの場合、手続きに時間がかかる場合があるので、タイミングを確認しましょう。
海外の子どもたちを支援するため、寄付をしよう

この記事の内容を改めてまとめます。
- 海外の子どもの支援先は、教育、健康、人身売買、児童労働など課題別に様々な団体がある
- 自分が問題だと思うことに取り組んでいる、信頼できる団体を支援先に選ぶ
- お金でもモノでも寄付ができる。寄付の方法は様々。自分に合ったものを選ぶ。
ぜひあなたにぴったりな団体、チェックしてみてくださいね!
▼この記事で紹介したおすすめ団体
| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |
|---|---|
| 日本ユニセフ協会 | ・国連機関ならではのスケールの大きな質の高い支援ができる。2019年のワクチンの供給数は24億回 ・マンスリーサポート(月2,000円など、寄付額は任意)でできることが具体的に示され、支援の成果の報告が充実 ・著名人(親善大使を担う人もいる)、企業・団体などユニセフの多くの支援者の存在 |
| ワールド・ビジョン・ジャパン | ・途上国の子どもと心のつながりを持ちながら、支援の成果を感じられる寄付プログラム「チャイルド・スポンサーシップ」に約5万人が参加・「1日あたり150円の支援で、子どもたちの未来が変わります」「何もかもはできなくとも、何かはきっとできる」などのメッセージから団体が大切にしていることが伝わる・「10秒に一人/1日に3つの学校にきれいな水を届ける」「貧困の根本原因を解決することで2億人以上の子どもたちの生活状況が改善」「極度の栄養不良にあった子どもたちの89%が完全に改善」など、活動の影響を具体的な数字で示している |
| e-Education | ・バングラデシュの教師不足の課題に、日本の予備校モデルを応用した遠隔型教育を10年以上前に開拓 ・若者3人が立ち上げ、多様な経験・経歴のスタッフが参画、100人のチームの規模、1,000人以上のマンスリーサポーターにまで発展 ・環境の変化に合わせて「最高の教育」を提供する方法を進化させながら、設立から10年で3万人以上の子どもに教育を届ける。受賞歴も多い |
寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー
大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。
寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。
大阪マラソンチャリティ事務局担当や、国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。