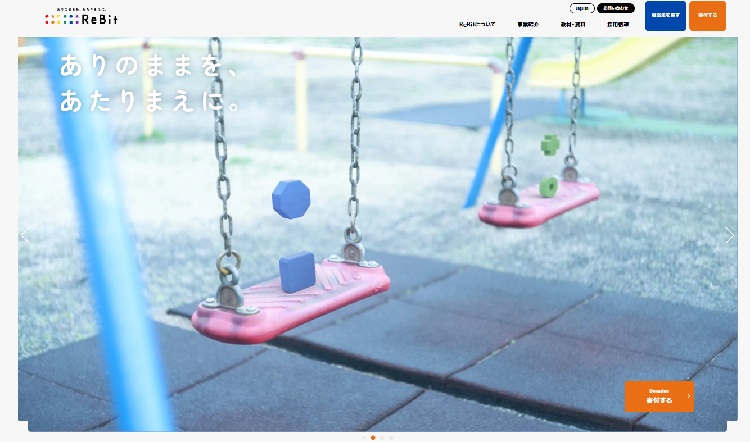性別に関する固定的なイメージや社会制度のなかで、自分の性自認と向きあいながら生きるトランスジェンダーの方たちは、日常生活のなかで、就職、教育、医療、婚姻など、さまざまな壁に直面しています。
こうした現実を知り、
「トランスジェンダーって、そもそもどういう意味?」
「性同一性障害やXジェンダーとは何が違うの?」
と感じたあなたへ向けて、本記事では以下の内容をわかりやすく整理しました。
- ・トランスジェンダーの定義と類似用語との違い
- ・トランスジェンダーが直面する問題
- ・トランスジェンダーを取り巻く論争
- ・トランスジェンダーを支援する団体の紹介
多様な性のあり方を知ることは、誰かの生きづらさを減らす一歩にもなります。まずは「知ること」から、理解と尊重の輪を広げていきませんか?
トランスジェンダーとは?
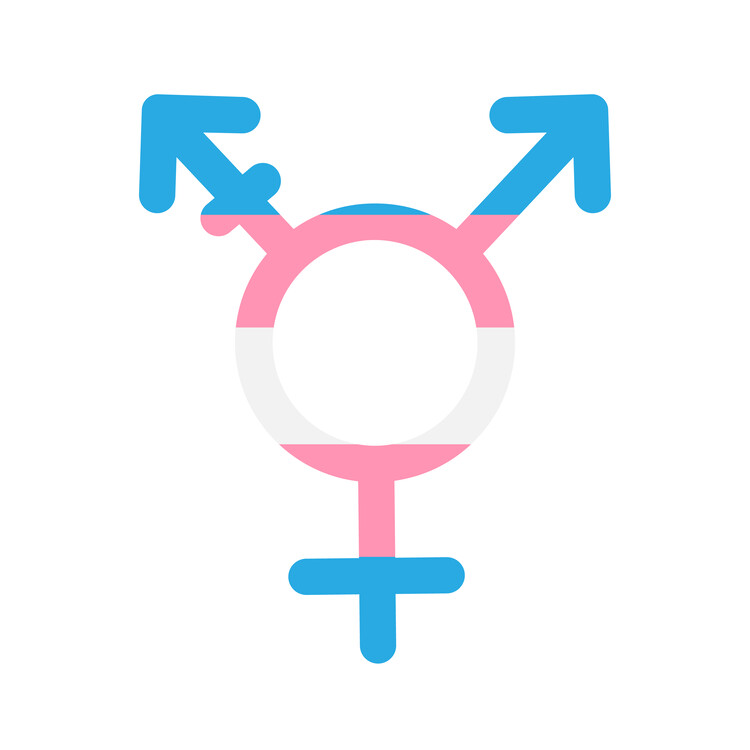
| 頭文字 | セクシュアリティ | 説明 |
|---|---|---|
| L | レズビアン(Lesbian) | 心と身体の性が女性で一致し、恋愛対象が女性である女性。同性愛者のひとつ。 |
| G | ゲイ(Gay) | 心と身体の性が男性で一致し、恋愛対象が男性である男性。同性愛者のひとつ。 |
| B | バイセクシャル(Bisexual) | 心と身体の性が一致しており、恋愛対象が男性・女性の両方に向く両性愛者。 |
| T | トランスジェンダー(Transgender) | 身体の性と心の性(性自認)が一致しない人。性自認に沿って生きたいと望む人が多い。 |
| Q | クエスチョニング/クィア(Questioning/Queer) | 性自認や性的指向が定まっていない、または伝統的な枠に当てはまらない人。 |
トランスジェンダーとは、身体の性別と、自分自身が認識している心の性別・性自認が一致しない人のことを指します。英語表記は「Transgender」で、LGBTQの「T」に当たるのがトランスジェンダーです。
特に「身体が男性で性自認が女性」の人を「MtF(Male to Female)」、「身体が女性で性自認が男性」の人を「FtM(Female to Male)」と呼びます。
なお、身体的性と性自認が一致している場合は「シスジェンダー」と呼ばれます。
「LGBTQ+」については、以下の記事で詳しく解説しています。
>>LGBTQIAとは?多様化する性的マイノリティへの理解を深めよう
トランスジェンダーと類似用語との違い

トランスジェンダーと混同されやすい言葉がいくつかあります。ここでは、
- ・トランスセクシャルとの違い
- ・Xジェンダーとの違い
- ・クロスドレッサーとの違い
- ・性同一性障害との違い
について、それぞれ整理しながら解説します。
トランスセクシャルとの違い
トランスセクシャル(TS)は、性同一性障害のひとつです。身体の性と心の性が一致せず、特に外科的手術によって、身体の性を心の性に一致させることを望む人を指します。
一方、トランスジェンダーは、外科的手術を希望するかどうかにかかわらず、自認する性が出生時の性と異なる人全般を含む、より広い概念です。
Xジェンダーとの違い
Xジェンダーは、以下のような人に当てはまります。
- ・自分の性別を男性でも女性でもないと認識している人
- ・どちらとも言い切れないと感じている人
- ・既存の性別の枠組みに分類されたくないと考える人
トランスジェンダーが主に男女間で性別の不一致を感じているのに対し、Xジェンダーは男女という枠を超えた性自認を持っています。
クロスドレッサーとの違い
クロスドレッサーは異性の服装を身につける人で、異性装者とも呼ばれます。趣味やファッションなどの理由で、異性の服装を楽しむ人です。
かつては「服装倒錯者」を意味するトランスベスタイトとも呼ばれていましたが、現在では差別的用語として、ほとんど使われなくなっています。
性同一性障害との違い
「性同一性障害」あるいは「性別違和」は、身体と心の性別が一致しない状態を指す医学的な診断名です。トランスジェンダーが自己認識や社会的な立場を表す概念であるのに対し、性同一性障害は医療的な文脈で使用されます。
日本では2004年7月に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(性同一性障害者特例法)が施行され、一定の条件下で、法令上の性別変更が可能となりました。
トランスジェンダーが抱える問題

トランスジェンダーの方たちは、さまざまな場面で課題に直面することがあります。主な例は以下のとおりです。
- ・婚姻
- ・就職や職場での差別
- ・学校の制服・いじめ
- ・医療費の負担
それぞれ詳しく解説します。
婚姻
日本国憲法では、婚姻は「両性の合意」に基づくと規定されており、同性同士の婚姻は現状認められていません。
そのため、トランスジェンダーの人が性別移行をしていない場合や、戸籍上の性別変更ができていない場合には、法律上の婚姻が難しくなることがあります。
一方で、2015年に渋谷区が初めて導入した「パートナーシップ制度」は全国に広がり、2024年9月時点で278の自治体が導入しています。
さらに、現行の同性婚を認めない制度を違憲とする判決も相次いでおり、同性婚をめぐる議論は今も続いています。
日本の婚姻制度については、以下の記事でも詳しく解説しています。
>>日本における同性婚やLGBTQ+への対応は?海外の結婚制度と比較
就職や職場での差別
職場でのトランスジェンダーに対する理解不足や差別は、深刻な問題です。
過去には、性同一性障害のある労働者が、服装の指示に従わなかったことを理由に懲戒解雇され、その処分が無効とされた裁判例もあります。
また、職場ではプライベートな話題に触れることも多く、性自認を偽って会話することは人間関係の構築を難しくするだけでなく、職場での孤立や転職のきっかけにもなりかねません。
職場での理解不足や偏見は、トランスジェンダーの方が安心して働く環境づくりを妨げる大きな要因となっています。
学校の制服・いじめ
「多数派」と異なることを理由にしたいじめは、トランスジェンダーの子どもにとって深刻な問題です。制服が自認する性と一致しないことで、日常的に強いストレスや苦痛を感じるケースもあります。
近年では女子生徒がスラックスを選べる学校が増えてきた一方で、男子生徒がスカートを選べる学校は、いまだほとんどありません。
こうした制服の選択肢や周囲の無理解は、学校生活における孤立や不安感につながる大きな要因となっています。
医療費の負担
トランスジェンダーが性自認に合わせた身体を得るためには、医療的介入が必要になります。しかし基本的に、こうした治療は保険適用外です。
また同性婚が法的に認められていない現状では、パートナーが入院した際も家族としては扱われません。パートナーの医療情報の提供を受けられなかったり、手術などの同意ができなかったりといった問題も発生しています。
LGBTQ+の人が抱える課題は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご一読ください。
>>LGBTQ+に関する課題とは?ジェンダー平等に向けた知識や活動を知ろう
トランスジェンダーを取り巻く論争

トランスジェンダーへの理解が少しずつ進む一方で、以下のような場面では社会的な議論や対立が生じています。
- ・トイレ・浴場問題
- ・スポーツ出場における公平性
どのような問題が起きているのかを見ていきましょう。
トイレ・浴場問題
トイレや公衆浴場は、利用のしにくさや不安を感じる人がいることから、たびたび議論の的となっています。新宿歌舞伎町の「ジェンダーレストイレ」は、わずか4か月で廃止されました。
一方で、誤解や偏見によって不安を煽る形で取り上げられることも多く、すべての人のプライバシーを守る環境整備には課題が残されています。
スポーツ出場における公平性
アメリカでは、トランスジェンダー選手の女子競技への参加をめぐって議論があり、トランプ大統領が反対の立場を表明。有力紙の世論調査では、約8割が否定的な意見を示したと報じられました。
一方、東京五輪では、性別適合手術を受けた選手が初めて出場し、大きな注目を集めました。
競技における公平性と、誰もが参加できる環境づくりの両立については、現在も国内外で議論が続いています。
トランスジェンダーの人が性別を変更するには?

トランスジェンダーの方が自らの性別を変更するためには、以下の方法があります。
- ・性別適合手術を受ける
- ・戸籍上の性別を変更する
それぞれ詳しく解説します。
性別適合手術を受ける
性別適合手術は、身体の外見を自認する性に近づけるための医療的手段です。代表的な施術には、乳房や性器の形成・切除などがあり、本人の希望する性別に沿った身体的特徴を得ることを目的としています。
ただし、現在の医学では生殖機能(妊娠する・させる能力)を得ることは困難とされており、手術はあくまで身体の見た目を性自認に近づけるものです。
戸籍上の性別を変更する
日本では「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に基づき、一定の条件を満たすことで戸籍上の性別変更が可能です。ただし、現行法では以下の5つの条件をすべて満たす必要があります
- 18歳以上である
- 結婚していない
- 未成年の子どもがいない
- 生殖腺(卵巣や精巣)を取り除いている
- 体の外見が希望する性別に近い
出典:e-Gov法令検索(政府サイト)「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」
トランスジェンダーの人が性別を法的に変更するには、現在も厳しい条件を満たす必要があります。
ただし、2023年には生殖腺の除去要件について最高裁が違憲の可能性を指摘しており、見直しに向けた議論が進みつつあります。今後、制度の改善や条件の緩和が期待されています。
トランスジェンダーについてよくある質問(Q&A)

ここではトランスジェンダーについてよくある以下の疑問にお答えします。
- ・トランスジェンダーはどうやってわかるの?
- ・トランスジェンダーの人と接するうえで心がけたいことは?
- ・トランスジェンダーの性別変更に手術は必要?
トランスジェンダーはどうやってわかるの?
トランスジェンダーかどうかは、自分自身の性自認によってわかるもので、他人が決めるものではありません。 一方、性同一性障害(性別違和)の診断は、医師が行います。
医師の診断により、心理的サポートやホルモン療法、外科手術などが受けられるようになります。
トランスジェンダーの人と接するうえで気をつけたいことは?
個人レベルでは、基本的には相手が自認している性別に則した接し方が望まれます。トランスジェンダーに関する話題は非常にデリケートであり、噂話のような感覚で話すべきではありません。
企業や組織としては、個人情報としての扱いに注意が必要です。すでにトランスジェンダーの従業員がいることを前提に考え、職場全体で理解を深める取り組みを行いましょう。
トランスジェンダーの性別変更に手術は必要?
これまで日本では、戸籍上の性別を変更するには生殖腺の除去や性器の外観変更などの手術が必要とされてきました。
しかし2023年には最高裁が生殖腺除去要件を違憲と判断し、2024年には性器の外観要件にも問題提起がされました。また立憲民主党などからは、手術要件の緩和を目指す法改正案も提出されています。
こうした動きを受け、今後は身体的な手術を前提としない性別変更が認められる可能性も高まりつつあります。
LGBTQの理解を広めるために活動する団体3選
ここからは、トランスジェンダーを含むLGBTQの理解を広めるために活動する団体を紹介します。専門家やgoododoマガジンの注目ポイントも参考にしてください。

認定特定非営利活動法人ReBit:LGBTQもありのままで未来を選べる社会を目指して
ReBitは、LGBTQもありのままで未来を選べる社会を目指し、教育・キャリア・福祉・まちづくり事業を展開するLGBTQ分野最大の認定NPO法人です。
代表自身がトランスジェンダーであり、幼少期から性別への違和感を誰にも相談できず、高校時代に自殺未遂を経験しました。「違いを持つ子どもたちも、ありのままで大人になれたら」との願いから、20歳のときに早稲田大学の学生団体としてReBitを設立。
団体名には、「少しずつ(Bit)」を「何度でも(Re)」繰り返し、社会を前進させる願いが込められています。2009年より、LGBTQが自分らしく学ぶ・働く・暮らすための環境づくりに取り組んでいます。
これまでに、1.8万人を超える困窮や精神的困難を抱えるLGBTQ当事者へのキャリア支援も行ってきました。
ReBitは、LGBTQの支援にとどまらず、多様性が尊重される社会の実現を目指し、教育機関や企業、行政と連携しながら、LGBTQへの理解促進や支援活動を進めています。
- 代表であり創設者の薬師実芳さんは、2015年に「青年版国民栄誉賞」とも称される「人間力大賞」を受賞。ダボス会議の若手リーダーによる国際ネットワーク「グローバル・シェーパーズ」や、オバマ財団の「アジア・パシフィック・リーダー」にも選ばれている。
- 2009年に学生団体として早稲田大学で産声を上げ、16年にわたりLGBTQと教育分野に取り組み(2,200回・22万人以上に授業を提供、LGBTQも安心できる学校づくりを支える教職員の育成と伴走も行う)、設立当初からの夢であった「教科書にLGBTQを載せる」ことも教科書会社と連携しながら達成。
- 事例集「自治体LGBTQ/SOGIEできることハンドブック」の公開や、中央省庁や200以上の自治体と連携し、LGBTQに関する研修や施策づくりを支援。LGBT理解増進法(2023年6月23日交付・施行)の策定に向けたプロセスにおいて、岸田総理(当時)との意見交換にも参加している、
公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本:不合理な差別や暴力に苦しむ人を支援

アムネスティ・インターナショナル日本は、世界中で、人権侵害の実態に関する独自調査、人権教育、キャンペーン、政府などへの提言などに取り組んでいます。
1961年に発足した世界最大の国際人権NGOで、世界200か国で700万人以上が活動に参加しています。国境を越えた自発的な市民運動が評価され、1977年にノーベル平和賞を受賞しました。
不偏不党、独立した立場で活動を行っているため政府からの援助は一切受けずに活動しています。
アムネスティ・インターナショナル日本はすべての人が世界人権宣言にうたわれている人権を享受でき、人間らしく生きることの世界の実現を目指して活動しています。
またアムネスティは、LGBTQ+の人権擁護 を掲げ、良心の囚人の釈放活動 や LGBTQ+の人権活動家の支援 に取り組んでいます。さらに、国際的なロビー活動と政策提言 を通じて各国の法改正を促し、世界的な監視と報告 によりLGBTQ+の人権侵害を記録・発信しています。
人権教育とキャンペーン を実施し、LGBTQ+の権利向上を目指しています。
- 有刺鉄線は「自由を奪われた人びと」を、そして、ろうそくは暗闇を照らす「希望」を表現したロゴマークに込めたメッセージに共感
- 活動資金は、中立性を保つためすべて寄付、会員の会費、活動収入で賄われる
- 寄付の他にも、オンラインアクション(署名)やキャンペーン参加など、「誰か」の絶望を希望にかえる。アクションの紹介が特徴
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら:【実際どう?】アムネスティの気になる評判は?寄付先として信頼できるかを徹底解説
特定非営利活動法人 Dialogue for People(D4P):無関心を関心に変え、共に社会を動かすメディア型NPO
Dialogue for People(D4P)は、戦争や差別、貧困など、困難な状況に置かれた人々や社会課題の渦中にある地域に足を運び、対話を重ねながら、写真・文章・動画・音楽といった多様な表現で「伝える」活動を行っている団体です。
現場で得た声や視点を丁寧に届けることで、遠い世界の出来事を自分ごととして考え、社会課題の解決につながるきっかけをつくっています。
トランスジェンダーを含む性的マイノリティの声を可視化する取材や発信も実施。人権や社会課題に関するドキュメンタリーや記事を通じて、多様な生き方への理解を広げる活動を続けています。
「すべての人の基本的人権が守られ、さまざまな違いを超えて多様性が認められる世界」を目指しています。
- 「伝えること」を中核に、社会の無関心に向き合い、無関心を関心に変え、社会に対話の礎を築くことをめざして活動するメディア型NPO。多様な専門性と属性の発信者が、光の当たりにくいテーマにも丁寧に取材・発信し、現場に根差したリアルな声を社会に届けている
- 社会課題と長期的な視点で向き合うために、次世代の「伝える人」の育成にも力を入れている。「育成」と「発信」を両輪に、持続可能な社会づくりに寄与するNPOとしての土台を着実に築いている
- 自らの「足りない部分」や「課題」にも真摯に向き合いながら丁寧な改善を重ねる「等身大の姿勢」が特徴。発信力だけでなく、NPOとしての組織運営にも誠実に取り組み、信頼と持続可能性を築いている
トランスジェンダーへの理解を深め、多様性を尊重する社会へ

本記事では、トランスジェンダーについて以下のようなポイントを解説しました。
- ・トランスジェンダーとは、性自認と身体の性が一致しない人のことを指す
- ・トランスジェンダーは、婚姻・就労・医療など、制度や社会の枠組みによって不利益を受けやすい現状がある
- ・トランスジェンダーを含むLGBTQの理解を広める団体がある
多様な性のあり方を正しく理解することは、誰もが安心して自分らしく生きられる社会づくりにつながります。
一人ひとりが正しく知り、相手の立場を想像することから、共に生きる社会を育てていきましょう。
▼LGBTQの理解を広めるために活動する団体
| 団体名 | 寄付アドバイザーが見た注目ポイント |
|---|---|
| ReBit | ・代表であり創設者の薬師実芳さんは、2015年に「青年版国民栄誉賞」とも称される「人間力大賞」を受賞。ダボス会議の若手リーダーによる国際ネットワーク「グローバル・シェーパーズ」や、オバマ財団の「アジア・パシフィック・リーダー」にも選ばれている ・2009年に学生団体として早稲田大学で産声を上げ、16年にわたりLGBTQと教育分野に取り組み(2,200回・22万人以上に授業を提供、LGBTQも安心できる学校づくりを支える教職員の育成と伴走も行う)、設立当初からの夢であった「教科書にLGBTQを載せる」ことも教科書会社と連携しながら達成 ・事例集「自治体LGBTQ/SOGIEできることハンドブック」の公開や、中央省庁や200以上の自治体と連携し、LGBTQに関する研修や施策づくりを支援。LGBT理解増進法(2023年6月23日交付・施行)の策定に向けたプロセスにおいて、岸田総理(当時)との意見交換にも参加している |
| アムネスティ・インターナショナル日本 | ・有刺鉄線は「自由を奪われた人びと」を、そして、ろうそくは暗闇を照らす「希望」を表現したロゴマークに込めたメッセージに共感 ・活動資金は、中立性を保つためすべて寄付、会員の会費、活動収入で賄われる ・寄付の他にも、オンラインアクション(署名)やキャンペーン参加など、「誰か」の絶望を希望にかえる。アクションの紹介が特徴 |
| Dialogue for People(D4P) | ・「伝えること」を中核に、社会の無関心に向き合い、無関心を関心に変え、社会に対話の礎を築くことをめざして活動するメディア型NPO。多様な専門性と属性の発信者が、光の当たりにくいテーマにも丁寧に取材・発信し、現場に根差したリアルな声を社会に届けている ・社会課題と長期的な視点で向き合うために、次世代の「伝える人」の育成にも力を入れている。「育成」と「発信」を両輪に、持続可能な社会づくりに寄与するNPOとしての土台を着実に築いている ・自らの「足りない部分」や「課題」にも真摯に向き合いながら丁寧な改善を重ねる「等身大の姿勢」が特徴。発信力だけでなく、NPOとしての組織運営にも誠実に取り組み、信頼と持続可能性を築いている |
寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん
NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー
大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。
寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。
国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。