街中で野良猫を見かけて
「外で暮らして危険はないの?」
「野良猫の寿命はどのくらい?」
そんな疑問を抱いたことはありませんか?実際、野良猫の寿命は平均3〜5年と短く、室内飼いの猫に比べて10年以上も差があると言われています。
その背景には、食糧不足や感染症、交通事故、過酷な気候など多くの危険が潜んでいます。
そこで本記事では、以下の内容を解説します。
- ・野良猫と室内飼い猫の寿命の違い
- ・野良猫の寿命が短くなる主な理由
- ・野良猫の寿命を延ばすためにできること
- ・野良猫の保護を検討すべき目安と支援団体の紹介
飢えや病気、事故の危険にさらされ、わずかな寿命しか全うできない野良猫たち。まずは現実を知り、自分にできる小さな一歩を考えてみませんか。
野良猫の平均寿命は?室内飼いの猫との違い

野良猫の寿命は室内で飼われる猫に比べてかなりの差があると言われています。まずは、その違いと背景にある生活環境について解説します。
野良猫の平均寿命は3~5年
野良猫の平均寿命はわずか3〜5年と、とても短いのが現実です。
屋外で暮らす野良猫は、交通事故や病気、飢えといった危険に常にさらされており、長生きすることが難しい環境にあります。気ままに暮らしているように見えますが、実際には過酷な生活の中で命を落とすことが多いのです。
室内飼いの猫との寿命差は10年以上
室内飼いの猫と野良猫は、生活環境の違いによって寿命に10年以上の差が生まれます。
室内飼いの猫は平均13〜15年、長ければ20年以上生きることもあります。長生きできるのは、危険の少ない環境で守られ、安定した食事や医療を受けられるためです。
一方で、過酷な生活環境こそが野良猫を短命にしているのです。
野良猫の寿命が短くなる主な理由

自由に生きているように見える野良猫ですが、平均寿命が短いのには、以下のようなさまざまな要因があります。
- ・食料不足や栄養失調による体力低下
- ・感染症や寄生虫による病気
- ・暑さ・寒さなど過酷な気候の影響
- ・交通事故などによる致命的な怪我
- ・縄張り争いや喧嘩による怪我
詳しく見ていきましょう。
食料不足や栄養失調による体力低下
野良猫の寿命が短い理由のひとつは、安定した食料を得られないことです。毎日食料を自分で探さなければならず、十分に食べられないことで体力が落ち、病気や怪我への抵抗力が弱まってしまいます。
野良猫の食料源は主にネズミや昆虫、小鳥、カエルなどですが、人間が与える食事のように栄養が十分ではなく、細菌感染のリスクもあります。
たまに人から餌をもらったり、生ゴミや残飯にありつけることもありますが、常に安定して食べられるわけではありません。
そのため栄養不足になりやすく、抵抗力が落ちて命を落とすことも少なくないのです。
感染症や寄生虫による病気
屋外で暮らす猫たちは衛生環境が悪いため、感染症や寄生虫による病気で命を落としやすくなっています。室内飼い猫のように予防接種も受けられず、自己免疫だけで病気に対抗しなければなりません。
屋外の生活ではノミ、ダニ、シラミによる病気にかかりやすいですが、猫エイズと呼ばれる免疫不全ウイルス感染症や猫白血病ウイルス感染症(FeLV)など深刻な病気に感染してしまうこともあります。
そのほか母子感染や喧嘩による傷、感染動物の捕食など、野良猫特有の生活環境が感染症の大きな原因となっています。
暑さ・寒さなど過酷な気候の影響

屋外の生活の野良猫は、過酷な気候の暑さ・寒さを直接受けるため命の危険にさらされやすくなります。
猫の汗腺は肉球にしかなく、体温調節は主に毛づくろいの唾液蒸発や日陰で休む、涼しい地面に体をつけるといった方法に頼っています。そのため、猛暑や高湿では放熱が追いつかず、熱中症になることがあるのです。
猛暑日では水場不足による脱水や腎臓へのダメージ、アスファルトの照り返しによる火傷の危険性も上がります。
寒い冬には低体温症や水の凍結による脱水が命を脅かします。暖を求めて車のエンジンルームなどへ潜り込み、事故に遭うことも少なくありません。
このように過酷な気候も、野良猫の寿命を縮める要因となっているのです。
交通事故などによる致命的な怪我
野良猫は交通事故などで致命的な傷を負い、寿命を縮めることも少なくありません。怪我の原因は車だけでなく、エンジンルームや工場機械、農機具への巻き込み、電気設備での感電や火傷など多岐にわたります。
飼い猫のように病院へ連れて行ってもらえず、治療すれば助かるはずの命を落とすケースもあります。さらに怪我で動けなくなれば餌を確保できず、栄養失調で命を縮めることもあります。
このように、野良猫の屋外生活には常に大きな怪我や命の危険が潜んでいるのです。
縄張り争いや喧嘩による怪我
野良猫は食べ物や水、寝床、発情相手を巡り縄張り争いをしており、喧嘩による怪我が絶えません。特に発情期のオスは攻撃性が増し、複数のオスが一匹のメスをめぐって激しく争うこともあります。
噛み傷や刺し傷、失明などの重い怪我を負っても治療を受けられず感染症を引き起こし、命を落とすことも少なくありません。
また常に敵に襲われる緊張感の中で暮らす非常に強いストレスも野良猫の寿命を縮める要因となっています。
野良猫の寿命を延ばすには?

野良猫の寿命を伸ばすためには、健康を維持するためのケアが欠かせません。具体的には以下の3つが挙げられます。
- ・不妊・去勢手術(TNR活動)の実施
- ・ワクチン接種と定期的な健康チェック
- ・栄養バランスの取れた食事と清潔な水の提供
詳しく解説していきます。
不妊・去勢手術(TNR活動)の実施
野良猫の寿命を延ばす方法のひとつとして挙げられるのが、不妊・去勢手術を実施する「TNR活動」です。TNRとはTrap(安全に捕獲)、Neuter(不妊・去勢手術)、Return(元の場所へ戻す)の頭文字を取ったもの。
まず繁殖を止めることで数を増やさず、そのうえで地域で猫と共生する環境づくりを進めていくことを目的としています。
野良猫すべてにTNRを実施できれば、最終的に殺処分ゼロの実現にもつながります。
野良猫の繁殖を止めることは地域環境の改善や安全向上にも役立つことから、TNR活動を積極的に推進している自治体も増えています。
ワクチン接種と定期的な健康チェック
野良猫たちにもワクチン接種を行うことで、致死的な感染症や集団内での病気の蔓延を防ぐことができます。
定期的な健康チェックをすれば、病気や怪我を早期に発見して治療でき、命を守ることにつながります。
室内飼いの猫と同じように、予防と健康管理を徹底することが、野良猫の寿命を延ばすことになるのです。
栄養バランスの取れた食事と清潔な水の提供

野良猫の寿命を延ばすには、栄養バランスの取れた食事と清潔な水を与えることが欠かせません。十分な栄養と水分は免疫力を高め、臓器の健康維持やストレス軽減につながるためです。
また、毎日安全な食事をとることで感染症や慢性疾患にかかりにくくなり、怪我からの回復力も高まります。安定した食事と水の提供こそが、野良猫を健康にし寿命を延ばすことにつながります。
ただし、むやみに餌やりをするのは、かえって不幸な猫を増やすことにもなりかねません。詳しくは以下の記事をご一読ください。
>>野良猫への餌やりがダメな理由とは?適切な関わり方と地域猫活動も解説
安全で快適な生活環境の確保
野外でも安全で快適な生活環境を整えることで、野良猫の寿命を延ばすことができます。
具体的には、定期的な餌やりや糞尿場所の清掃、食べ残しの片付け、猫にとって危険なゴミの除去などの活動が効果的です。最終的に地域の美化や安全向上にも貢献します。
地域猫活動や支援団体への協力
野良猫の寿命を延ばすためには、地域住民による「地域猫活動」や支援団体への協力も効果的です。これらの活動では、適切な餌の提供やTNR活動(捕獲・不妊去勢・元の場所へ戻す)を通じて猫の命を守っています。
活動や団体に寄付や物資提供で支援すれば、現場での見守りや医療費の負担軽減につながります。その結果、野良猫の命をより長くつなぐことができるのです。
地域猫については、以下の記事で詳しく解説しています。
>>「地域猫」とは?耳カットの理由やさくら猫の意味、TNR活動について解説
野良猫の保護を考えるときの目安

野外で猫を見かけても、すぐに保護するのが最善とは限りません。以下の状況にある場合に、保護を検討すると良いでしょう。
- ・怪我・病気で衰弱している
- ・虐待や危害を受けている可能性がある
- ・母猫がいない子猫である
- ・子猫で交通事故の危険が高い
- ・飼い猫・地域猫ではないと確認できた
保護を検討する目安を詳しく解説していきます。
怪我・病気で衰弱している
見ただけで致命的な怪我や病気で衰弱していることがわかる野良猫は、保護を検討してみてください。
ただし、病気や怪我が感染しないよう安易に手を出さないことが大切です。まずは野良猫をよく観察し、自治体の動物愛護センターや保健所などに連絡して判断しましょう。
虐待や危害を受けている可能性がある
野良猫に刃物で切られたような傷や火傷など、不自然な怪我が見られる場合は、人間から虐待や危害を受けている可能性があります。
そのような場合は、保護を検討するほか、地方自治体の通報窓口や警察に相談・通報することも重要です。
動物虐待については、以下の記事で詳しく解説しています。
>>動物虐待とはどんな行為?種類や私たちにできることを解説
母猫がいない子猫である

母猫が近くにおらず数時間様子を見ても現れない子猫は、保護を検討してみてください。
子猫は母猫の授乳がないと栄養失調や低体温症になったり、カラスや犬など外敵に襲われる恐れもあるため、一匹でいるのは危険です。
子猫で交通事故の危険が高い
子猫は危険を理解できないため、交通事故に遭いやすい傾向があります。体が小さく動きが遅いうえ、運転手からも見えにくいため、車に引かれやすいのです。
子猫は好奇心が旺盛なため、車道に飛び出してしまうことも少なくありません。親猫がいないかを確認しつつ、早めに保護を検討することが大切です。
飼い猫・地域猫ではないと確認できた
飼い猫・地域猫ではないとわかった場合、健康的に地域で暮らせるよう保護を検討しても良いでしょう。
飼い猫がどうか見分けるポイントは、清潔さや首輪の有無、人への警戒心の強さなどです。また地域猫は不妊・去勢手術済みの印として、片耳がカットされているのが特徴です。
ただし、これらに当てはまらない野良猫もいるため、猫を見つけた場合はすぐに判断せずしばらく観察することも大切です。
野良猫を保護するには、費用や準備が必要です。詳しくは以下の記事をご参照ください。
>>野良猫を引き取る保護団体はある?保護前に知っておきたい注意点も解説
野良猫の保護活動を行う団体5選
野良猫の命を延ばすための保護活動には、支援団体の存在が欠かせません。ここでは、野良猫を救うために日々活動している団体を5つ紹介します。
また寄付という形でこうした団体を応援することも、猫たちの命をつなぐ活動の力になります。各団体の活動内容や、NPOの専門家・gooddoマガジン編集部による注目ポイントも参考にしてみてください。

公益財団法人どうぶつ基金:保護・避妊・啓発を通じて殺処分される猫を減らす

公益財団法人どうぶつ基金は、野良猫の繁殖を抑制するための無料不妊手術事業「さくらねこ活動」を中心に活動しています。また、多頭飼育崩壊の救済支援や保護猫の里親マッチング、動物愛護に関する普及啓発活動を通じて、人と動物が共生できる社会を目指しています。
35年以上の長い歴史があり、活動報告書や会計報告書を詳細に公開していることから、信頼性の高い活動実績を持つ団体です。殺処分ゼロを目指し、多様なボランティアが協力して取り組む点が大きな特徴です。
- 無料不妊手術(TNR)という方法で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざしている
- 広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している
- 行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている
どうぶつ基金の口コミが知りたい方はこちら
>>どうぶつ基金は怪しい?活動実態や口コミ評判を調べてみた
ピースニャンコ(認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン):医療支援をもとに保護猫ボランティアをサポート

ピースニャンコは、保護猫ボランティアを医療面からサポートする活動を行っています。
自然災害や紛争の被災地支援活動を行う、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営しているプロジェクトです。保護犬を支援するプロジェクトにはピースワンコがあり、既に蓄積されたノウハウがあります。
ピースニャンコでは、動物病院での診療費支援や不妊・去勢手術の費用援助を実施。ピースワンコの譲渡センターを活用した医療支援を通じて、保護猫の健康管理をサポートしています。
保護猫ボランティアの負担軽減を図りながら譲渡促進にも取り組み、1匹でも多くの保護猫が新しい家庭で幸せに暮らせる未来を目指しています。
- 不妊・去勢手術の費用や治療費の支援で、猫の殺処分を減らしている
- 災害時の緊急保護や医療支援にも対応し、猫の命を守る体制づくりに取り組んでいる
- 保護猫ボランティアと連携しながら、現場の声を反映した支援の仕組みを広げている
保護犬を殺処分から救うピースワンコの口コミを知りたい方は、こちらをご一読ください。
>>【怪しい?】ピースワンコ・ジャパンの口コミ評判は?専門家に詳しく聞いてみた
特定非営利活動法人 犬猫みなしご救援隊:行き場のない犬猫専用の「終生飼養ホーム」を運営
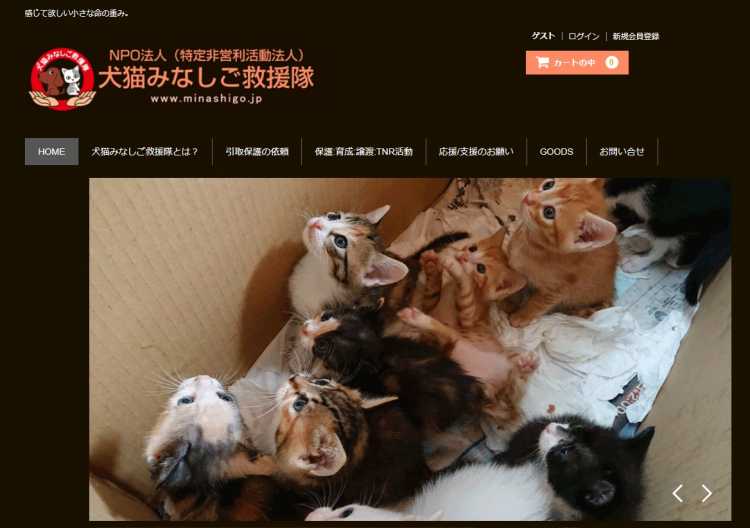
一般家庭では飼養が困難な、引き取り手のない犬猫たちを積極的に保護し、命が尽きる時まで責任を持って育てる「終生飼養」や猫の譲渡活動、野良猫の不妊手術などを行っています。
動物と人間が共生できる明るい未来の実現を目指しています。
- 障害や傷病を負っていたり、人になつかない野良犬や野良猫など、引き取り手のない犬・猫たちの受け皿として、犬猫専用の「終生飼養ホーム」を運営している
- 犬や猫だけでなく、ウサギ、鹿、ハクビシンなどの動物の引き取りも行っている
- オリジナルグッズの購入を通して、活動を応援できる。エコバッグ、Tシャツ、書籍、サーモスボトルなど種類豊富
公益財団法人 日本動物愛護協会:人と動物が共に生きられる社会を目指す

幸せな動物を増やすため、犬や猫の譲渡会の開催、災害時の動物救援、動物愛護講座の開催を始めとした啓発活動、日本動物大賞・動物愛護表彰などを通した提言活動を行っています。
1948年に設立され、70年以上も動物愛護の活動を継続している歴史と実績のある団体です。
「今を生きている命は幸せに、不幸な命は生み出さない!」をスローガンとした活動を通し、人と動物が共に生きられる社会を目指しています。
- 動物に関わる相談をメールや電話で受け付け、アドバイスを行っている
- 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の助成を行い、人間の都合で不幸になってしまう猫を減らしている
- 1948年に設立され、70年以上も動物愛護の活動を継続している歴史と実績のある団体
NPO法人犬と猫のためのライフボート:20,000頭以上の里親探しの実績あり

NPO法人犬と猫のためのライフボートは、保健所からの保護犬・猫の救命と譲渡を20年以上行う団体であり、今までに22,477頭の譲渡実績があります。
保護から医療、譲渡までを総合的にケアし、施設内には動物病院も併設。全国7か所の保健所と連携し、殺処分を防ぐ活動に取り組んでいます。
- 動物病院の併設により健康面のサポートをしている
- 長年にわたり里親探しの実績がある
- 幅広い地域で活動している
野良猫の寿命を延ばすために私たちができること

本記事では、野良猫の寿命について次のポイントをお伝えしました。
- ・野良猫の平均寿命は3〜5年と短く、室内飼い猫より10年以上も差がある
- ・野良猫の寿命が短い理由には、食糧不足・病気・事故や気候といった過酷な環境がある
- ・野良猫の延命のためには、TNR活動や健康管理、支援団体との協力が重要
野良猫の寿命を延ばすには、地域での見守りや活動に参加することが身近な一歩です。また支援団体へ物資の提供や寄付をすることで活動を後押しできます。
野良猫たちの命を守るために、できることから始めてみてはいかがでしょうか。
▼野良猫の保護活動支援におすすめの団体
| 団体名 | 寄付アドバイザー・gooddoマガジンの注目ポイント |
|---|---|
| どうぶつ基金 | ・無料不妊手術(TNR)で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざしている ・広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している ・行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている |
| ピースニャンコ | 不妊・去勢手術や治療費の支援で、保護猫の命を守り、殺処分を減らしている ・災害時の緊急保護や医療支援にも対応し、猫の命を守る体制づくりに取り組んでいる ・保護猫ボランティアと連携しながら、現場の声を反映した支援の仕組みを広げている |
寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん
NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/日本ファンドレイジング協会・認定講師・関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー
大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。
寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。
国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。
- gooddoマガジン編集部 の最近の投稿
-
高額寄付だからこそ、後悔しないための寄付先選びは慎重に。
2026年2月12日 2026年2月12日 Other -
ダイバーシティとは?意味や具体的な実践例を紹介
2026年2月4日 2026年2月4日 SDGs -
ピースニャンコは怪しい?口コミ評判や活動実態を調べてみました
2025年10月30日 2025年11月5日 寄付

