犬や猫は多くの家庭で飼われており、人のパートナーとして飼養されています。
一方で飼い主により捨てられ、行政機関に引き取られるといったことも起きています。
その犬や猫は引き取り手がいなかった場合、殺処分という形で命を奪われてしまうのです。
そうならないために、行政機関などでは殺処分ゼロに向けた取り組みが行われています。
この記事では、殺処分ゼロへの取り組みや具体例を紹介します。
猫や犬の殺処分の現状やできることについて知りたい方は、ぜひ以下の記事をご一読ください。
>>【6割が子猫】猫の殺処分の現状は?処分数の多い都道府県や猫を救うためにできること
>>【年間2,118頭】犬の殺処分の現状とゼロを目指す活動、私たちにできることを解説
動物愛護センターについては、以下の記事で解説しています。
>>動物愛護センターとは?活動内容や犬猫の譲渡方法などを紹介
「殺処分から犬たちの命を守る」
活動を無料で支援できます!
30秒で終わる簡単なアンケートに答えると、「殺処分から犬たちの命を守る」活動している方々・団体に、本サイト運営会社のgooddo(株)から支援金として10円をお届けしています!
設問数はたったの3問で、個人情報の入力は不要。あなたに負担はかかりません。年間50万人が参加している無料支援に、あなたも参加しませんか?
動物愛護センターの犬猫の殺処分の現状

人のパートナーとして古くから飼われることが多い犬、そして猫はブームもあり、近年飼われることが増えてきました。
1頭であれ多頭であれ、同じ飼い主によって世話をしてもらえれば良いのですが、現実には世話をしきれず捨てられ、保健所・動物愛護センターなどに引き取られる犬や猫もいます。
行政機関に引き取られた数は、2023年度で犬が1万9,352匹、猫は2万5,224匹にもなりました。
約20年前の2004年には犬が18万1,167匹、猫が23万7,246匹であったことを考えれば、大幅に減少したと言えるでしょう。
そして2023年度の殺処分件数は、犬が2,118匹、猫が6,899匹となりました。
引き取り件数から考えれば犬は多くが返還か新しい飼い主への譲渡が行われ、殺処分が抑えられていることが分かります。
殺処分件数は年々減少しており、20年前に比べれば大幅に減少していますが、まだ多くの犬猫たちが殺処分となっていることも事実です。
未だにゼロになることはなく、これだけの命が人の手によって奪われているのです。
そんな現状を改善するために国や都道府県などの行政機関では、いくつもの取り組みを進め、殺処分ゼロを目指した活動を進めています。
(出典:環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」,2023)
日本に逃れてきた難民を正社員として雇用。エシカルなPCでSDGsに取り組みませんか?
動物愛護センターなどの殺処分ゼロに向けた取り組み

犬猫の殺処分ゼロに向けた取り組みが本格的に始まったのは2013年11月です。
環境省自然環境局にある動物愛護管理室に「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」が立ち上げられました。
このプロジェクトでは、以下を目的としています。
犬猫の殺処分がなくなることを目指すための具体的対策について検討を行い、命を大切にし、優しさのあふれる、人と動物の共生する社会の実現を目指す。
(引用:環境省「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト ご挨拶」)
それまでは都道府県や市区町村にある保健所や動物愛護センターの各々の取り組みのみでしたが、環境省主導の取り組みとして、全国的な調査や現状の分析、課題の整理などを行い、その課題解決のための具体的対策の検討や、効果的な周知を行うための広報が行われています。
プロジェクトが主となって行政機関だけが殺処分ゼロを目指すのではなく、飼い主や事業者、ボランティアなどが一丸となって行う取り組みの展開と推進を進めています。
(出典:環境省「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト ご挨拶」)
殺処分を減らすための3つのポイント
人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトでは、殺処分ゼロを達成するために、取り組みを行う上での3つのポイントを定めています。
1つ目のポイントとして「飼い主や国民の意識の向上」が挙げられています。
動物を飼うということは命に対して責任を負わなければならず、適正な飼養や管理を行う必要があります。
また現行の動物愛護管理法では殺傷や虐待、遺棄は犯罪であり処罰の対象となることなど、飼い主となる上で知らなければいけないことがあまり普及していないことこそ殺処分がゼロにならない原因の一つとして考えられています。
そのため取り組みの一つとして、効果的な広報や普及啓発、教育の場における展開が行われているほか、9月には動物愛護週間での「どうぶつ愛護フェスティバル」などのイベントを行い、講演やディスカッション、体験を通した周知も行われています。
2つ目のポイントとしては「引き取り数の削減」を挙げています。飼い主の責任には適正な飼養や管理があり、最後まで世話をすることが求められています。
しかし実際には無責任な飼い主による遺棄で、多くの野良犬や野良猫が生まれる、あるいは動物愛護センターなどに引き取ってもらう現状があります。
不妊去勢手術が行われていなければ、繁殖によりさらに飼い主がいない犬猫が増え、殺処分へとつながる可能性が高くなります。
そうならないためにも、不妊去勢措置の徹底や猫の室内飼育、幼齢な犬猫の適正な取扱の推進などが行われています。
加えて3つ目のポイントとして、引き取った犬猫の所有者への「返還と適正譲渡の推進」も進められています。
この3つのポイントを進めることで、飼い主や国民の意識が高まり、無責任な飼養が減って引き取り数が大幅に削減できること、そして引き取った犬猫の返還・譲渡を進めることで、最終的な殺処分を行わなければいけない犬猫をゼロにすることを目指しています。
(出典:環境省「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト アクションプラン」)
殺処分ゼロに向けた具体的な取り組み:奈良市の例
奈良市では、「犬猫の殺処分ゼロ」を目指し、保護犬・保護猫の引き取り数の削減や譲渡機会の拡充など、さまざまな取り組みを進めてきました。こうした継続的な努力の結果、2023年度には自然死・安楽死を除く「殺処分ゼロ」を達成しています。これは2019年度から5年連続での達成となります。
取り組みとしてはいくつかありますが、その中の一つにミルクボランティア制度があります。
ボランティアによって生後2ヶ月まで保護された幼齢猫の、ミルク給餌や排泄の世話が行われます。このときのミルクは支給されるほか、ヒーターの貸し出しなども行われますが、2018年までに延べ58匹の幼齢猫が預けられました。
幼齢猫の世話は難しく、所有者不明の猫の中には幼齢猫が多くを占めているため引き取り手を見つけるためにも世話をする人が必要となりますが、それをボランティアにお願いしようという制度です。
そのような猫を含め、引き取られた犬猫に関して譲渡と相談を行う会が年6回開催されました。来場者は約60組おり、申し込み相談数は26匹にもなっています。
さらに遺棄を防ぐために、2018年6月から犬猫パートナーシップ店をスタートして、認定店での販売では終生飼育への誓約や、マイクロチップを装着した犬猫を販売する取り組みが行われました。
また不妊去勢措置のために、飼い主がいない猫への繁殖制限手術補助金も出されており、メスが44匹、オスは22匹の計66匹分が実施されました。
他県でも行われている同様の取り組みもありますが、このような取り組みを進めていくことで、奈良市では犬猫殺処分ゼロに限りなく近づく結果が出たのです。
(出典:奈良市「犬猫殺処分ゼロへの取り組みについて」)
【簡単5分でスタート】毎日使う電力を節約しながら平和のために活動するNPO・NGOに自動寄付
殺処分ゼロに向けた具体的な取り組み:名古屋市の例
名古屋市では犬猫殺処分ゼロを目指す取り組みの一つとして、犬猫サポート寄附金を設置しています。
2016年からスタートしたこの寄付金や譲渡ボランティア活動により、2025年までに犬の殺処分ゼロを継続しています。猫については未だに殺処分が行われている現状ですが、それでも目標に近づいていることは確かです。
この寄付金はふるさと納税を通じて行えるサポートであり、動物愛護センターなどが引き取り、譲渡先が見つかるまで預かっている犬猫の餌やペットシーツ、薬品、子猫のミルクの購入費、譲渡ボランティアの支援物資に充てられています。
これは動物愛護センターや譲渡ボランティアが粘り強く新しい飼い主を見つけるための活動に活かされています。
どうしても世話にはお金がかかるため、このような寄付金による支援は必要不可欠です。
この寄付金のおかげで犬猫はすぐに殺処分されることなく、飼い主が見つかるまで世話をしてもらえます。
たとえ新しい飼い主になれなくても、何かしら支援を行いたいということであれば、私たちにできるのはこのような寄付に協力することも一つです。
名古屋市では寄付以外にもクラウドファウンディングも始めていますが、自分が住む地域にも同じような取り組みがあれば、参加してみると良いでしょう。
(出典:名古屋市「目指せ殺処分ゼロ!犬猫サポート寄附金について」)
動物愛護センター以外にも!動物を殺処分から救う活動をする団体5選

保護犬や保護猫の殺処分をなくすために、多くの支援団体が日々活動を続けています。寄付という形で支援できるおすすめの団体を5つ紹介します。

ピースワンコ・ジャパン(認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン):支援者とのコミュニケーションを大切にしながら「犬の殺処分ゼロ」の実現を目指す
ピースワンコ・ジャパンは、「犬の殺処分ゼロ」の実現を目指し、犬の保護・譲渡活動を行っています。自然災害や紛争の被災地支援活動を行う、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営しているプロジェクトです。
災害救助犬やセラピー犬の育成、正しい飼い方や動物福祉の考え方の啓発活動などにも取り組んでいます。
ピースワンコ・ジャパンは、今まで8,000頭以上の犬の命を救ってきました(2024年1月末時点)。
プロジェクトの運営母体であるピースウィンズ・ジャパンは、広島県より認定NPOの認証を受けています。また、優れたソーシャルビジネスの取り組みを表彰する、日経ソーシャルイニシアチブの受賞歴もあります。
ピースワンコ・ジャパンは「犬と人がひとつになり、豊かな未来をつくろう」というメッセージを発信しながら、活動に取り組んでいます。
- 活動報告や今後の方針などのメールがこまめに配信されたり、YouTubeを始めとしたSNSでの発信も頻繁に行われている。団体とのつながりを感じながら支援できる
- 「日本での犬の殺処分ゼロ」を目指し、まずは広島県内で殺処分機を2016年4月から現在まで止めている。日本という大きな枠でのミッション実現に向け、まずは1つの県で達成できているのは大きな成果。
- ピースワンコ・ジャパンの毎月の継続寄付の会員「ワンだふるサポーター」は63,000人。多くの共感を呼ぶプロジェクトをしている、という実感が持てる。
ネットの口コミ評判を知りたい方はこちら
>>【怪しい?】ピースワンコ・ジャパンの口コミ評判は?専門家に詳しく聞いてみた
ピースニャンコ(認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン):医療支援をもとに保護猫ボランティアをサポート
ピースニャンコは、保護猫ボランティアを医療面からサポートする活動を行っています。
自然災害や紛争の被災地支援活動を行う、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営しているプロジェクトです。保護犬を支援するプロジェクトにはピースワンコがあり、既に蓄積されたノウハウがあります。
ピースニャンコでは、動物病院での診療費支援や避妊去勢手術の費用援助を実施。ピースワンコの譲渡センターを活用した医療支援を通じて、保護猫の健康管理をサポートしています。
保護猫ボランティアの負担軽減を図りながら譲渡促進にも取り組み、1匹でも多くの保護猫が新しい家庭で幸せに暮らせる未来を目指しています。
- 避妊去勢や治療費の支援で、保護猫の命を守り、殺処分を減らしている
- 災害時の緊急保護や医療支援にも対応し、猫の命を守る体制づくりに取り組んでいる
- 保護猫ボランティアと連携しながら、現場の声を反映した支援の仕組みを広げている
今なら毎月の寄付額に応じて、ステキなプレゼントを贈呈中!
- 月1,000円〜:オリジナルステッカー
- 月3,000円〜:ステッカー+記念チャーム
- 月5,000円〜:ステッカー+記念チャーム+西東京ふれあい譲渡センターに展示される記念モニュメントの1ピース

公益財団法人どうぶつ基金:保護・避妊・啓発を通じて殺処分される猫を減らす

公益財団法人どうぶつ基金は、野良猫の繁殖を抑制するための無料不妊手術事業「さくらねこ活動」を中心に活動しています。また、多頭飼育崩壊の救済支援や保護猫の里親マッチング、動物愛護に関する普及啓発活動を通じて、人と動物が共生できる社会を目指しています。
35年以上の長い歴史があり、活動報告書や会計報告書を詳細に公開していることから、信頼性の高い活動実績を持つ団体です。殺処分ゼロを目指し、多様なボランティアが協力して取り組む点が大きな特徴です。
- 無料不妊手術(TNR)という方法で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざしている
- 広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している
- 行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている
どうぶつ基金の口コミが知りたい方はこちら
>>どうぶつ基金は怪しい?活動実態や口コミ評判を調べてみた
特定非営利活動法人 犬猫みなしご救援隊:行き場のない犬猫専用の「終生飼養ホーム」を運営
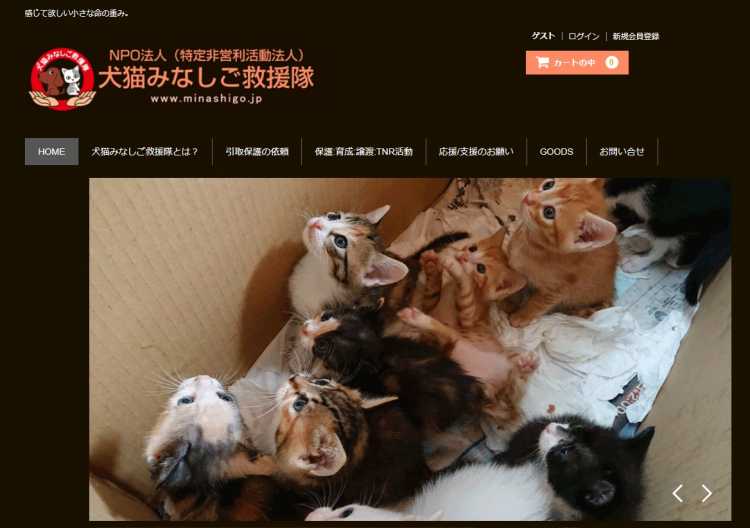
一般家庭では飼養が困難な、引き取り手のない犬猫たちを積極的に保護し、命が尽きる時まで責任を持って育てる「終生飼養」や猫の譲渡活動、野良猫の不妊手術などを行っています。
動物と人間が共生できる明るい未来の実現を目指しています。
- 障害や傷病を追っていたり、人になつかない野良犬や野良猫など、引き取り手のない犬・猫たちにの受け皿として、犬猫専用の「終生飼養ホーム」を運営している
- 犬や猫だけでなく、ウサギ、鹿、ハクビシンなどの動物の引き取りも行っている
- オリジナルグッズの購入を通して、活動を応援できる。エコバッグ、Tシャツ、書籍、サーモスボトルなど種類豊富
公益財団法人 日本動物愛護協会:人と動物が共に生きられる社会を目指す

幸せな動物を増やすため、犬や猫の譲渡会の開催、災害時の動物救援、動物愛護講座の開催を始めとした啓発活動、日本動物大賞・動物愛護表彰などを通した提言活動を行っています。
1948年に設立され、70年以上も動物愛護の活動を継続している歴史と実績のある団体です。
「今を生きている命は幸せに、不幸な命は生み出さない!」をスローガンとした活動を通し、人と動物が共に生きられる社会を目指しています。
- 動物に関わる相談をメールや電話で受け付け、アドバイスを行っている
- 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の助成を行い、人間の都合で不幸になってしまう猫を減らしている
- 1948年に設立され、70年以上も動物愛護の活動を継続している歴史と実績のある団体
動物愛護センターの殺処分ゼロのためにできることから始めよう

殺処分ゼロを目指す取り組みは、環境省をはじめ、各地の保健所や動物愛護センターによって進められています。ただし、行政の力だけでは限界があり、目標の実現には市民一人ひとりの協力が欠かせません。
その第一歩として、「殺処分ゼロ」を目指す団体への寄付という選択があります。
動物愛護の意味を知り、自分にできることから行動していくことが、犬や猫の命を守る力につながります。
▼動物の殺処分から救う活動をするおすすめ団体
| 団体名 | 寄付アドバイザー・gooddoマガジンの注目ポイント |
|---|---|
| ピースワンコ | ・活動報告や今後の方針などのメールがこまめに配信されたり、YouTubeを始めとしたSNSでの発信も頻繁に行われている。団体とのつながりを感じながら支援できる ・「日本での犬の殺処分ゼロ」を目指し、まずは広島県内で殺処分機を2016年4月から現在まで止めている。日本という大きな枠でのミッション実現に向け、まずは1つの県で達成できているのは大きな成果 ピースワンコ・ジャパンの毎月の継続寄付の会員「ワンだふるサポーター」は63,000人。多くの共感を呼ぶプロジェクトをしている、という実感が持てる |
| ピースニャンコ | ・避妊去勢や治療費の支援で、保護猫の命を守り、殺処分を減らしている ・災害時の緊急保護や医療支援にも対応し、猫の命を守る体制づくりに取り組んでいる ・保護猫ボランティアと連携しながら、現場の声を反映した支援の仕組みを広げている |
| どうぶつ基金 | ・無料不妊手術(TNR)で殺処分をなくし、動物が人や自然と自由に幸せに共生することができる世の中をめざしている ・広報とロビー活動を積極的に行い課題を発信している ・行政や他団体、獣医師、ボランティアとの連携・協働により活動を広げている |
寄付先の選び方ガイド:河合将生(まさお)さん
NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime代表/日本ファンドレイジング協会・認定講師・関西チャプター共同代表・准認定ファンドレイザー
大学卒業後、国際協力分野のNGOにボランティアスタッフとして参加。その後、国際交流・協力分野の中間支援組織へのインターンシップ、職員を経て、office musubime (オフィス ムスビメ)を2011年7月に設立。
寄り添って伴走する第三者として、身近な相談相手や多様な人・団体をつなぐ役割を通し、組織診断・組織基盤強化、ファンドレイジング支援など、各団体の支援に取り組む。
国際協力や子ども/子育て支援、まちづくり分野、コミュニティ財団などの役員、大学の非常勤講師としてNPO論やボランティア論などの担当も。
- gooddoマガジン編集部 の最近の投稿
-
高額寄付だからこそ、後悔しないための寄付先選びは慎重に。
2026年2月12日 2026年2月16日 Other -
ダイバーシティとは?意味や具体的な実践例を紹介
2026年2月4日 2026年2月16日 SDGs -
ピースニャンコは怪しい?口コミ評判や活動実態を調べてみました
2025年10月30日 2025年11月5日 寄付



