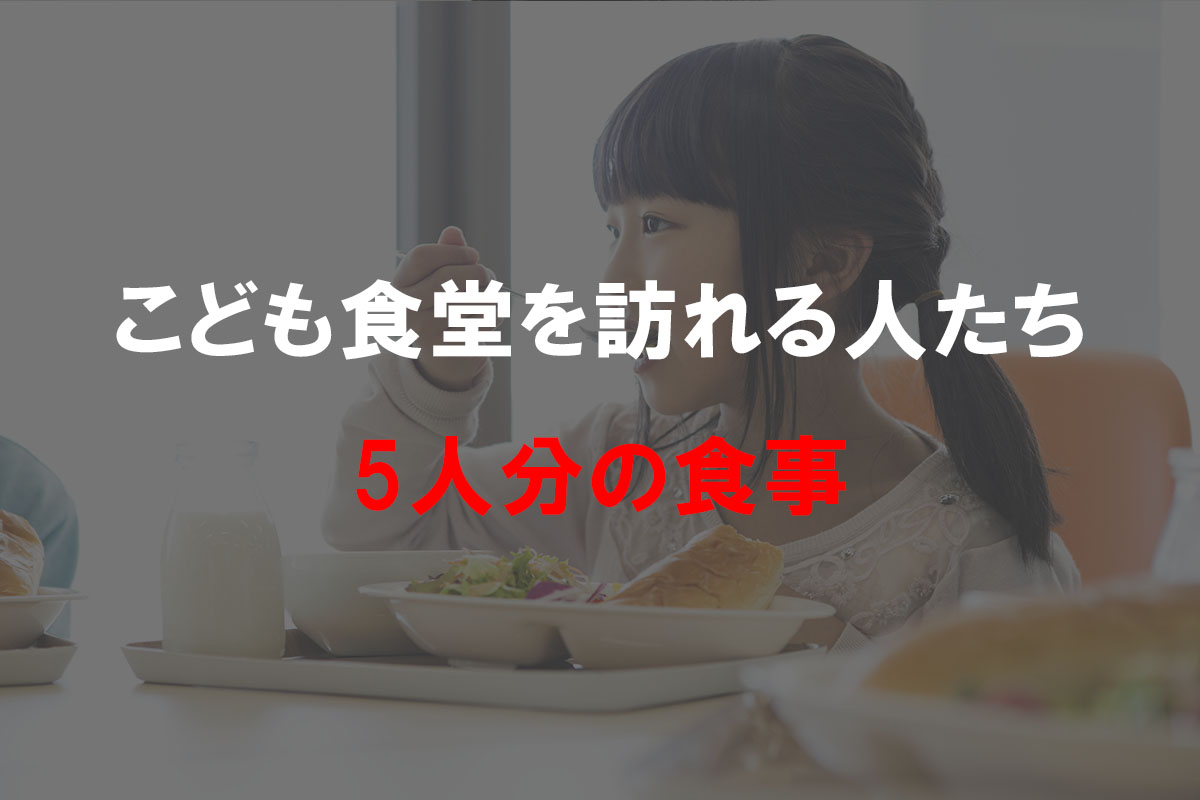<PR>
親を亡くした子どもたち、遺児の家庭で起きているコロナ禍の生活とは?
子供のアルバイトもすごく減っていて、お金の工面が大変。
また、万が一コロナにかかった場合や、濃厚接触者に家族がなってしまった場合、
すべての収入が減ってしまうのがこわい
40代・女性
助けてください
今のままでは自殺しかない。
50代・女性
遺児家庭とは、病気や災害、または自死により親を突然亡くした子どもたち(遺児)の家庭のことです。(または両親もしくは片親に障がいがあるご家庭)
急な環境の変化、そして親を亡くすという大きなショックを抱えながら、それでも必死に生きる子どもたち。
伴侶を亡くし、深い悲しみに暮れている時間もなく、残された子どもたちを育てるために仕事に追われる親たち。
このような遺児家庭が、コロナ禍で経済的により追い詰められています。
昨年秋に実施された一般社団法人あしなが育英会の調査では、遺児家庭の平均月収は、14.7万円であり、一般労働者の24.5万円(*)と比べると約10万円も低いのです。
*賃金構造基本統計調査(2020, 厚労省)の平均賃金30.77万円より推計
さらに、「遺児の保護者の4人に1人以上が昨年9月の収入がゼロ」、「5人に1人がコロナ禍で雇止めや転職を経験した」など、コロナ禍における遺児家庭の窮状が浮き彫りにされました。
約6割の保護者が非正規雇用と、コロナ以前から経済的に弱い立場にあった遺児家庭は、コロナによりさらに困窮をきわめています。
「大学には行かせてあげたい」、経済的に苦しい中でも「子どもの夢は叶えてあげたい」と懸命に働く保護者たち

遺児家庭であろうと、親が我が子を思い、「夢を叶えるために手助けしたい」「大学に行かせてあげたい」、そう考えるのは、普通のことではないでしょうか。
18歳になると、遺族年金の支給が終了となります。大学進学に必要な経費も遺児家庭には大きな負担となり、さらに経済的に苦しい状況に追い込まれてしまいます。
それでも、「子どもに夢をあきらめてもらいたくない」と、保護者は自身の時間を惜しまず、自身の健康状態に目を瞑りながら、働き続けています。
非正規雇用が多い遺児家庭の保護者は、いくつもの仕事を掛け持ち、体を壊してしまう方も少なくありません。
教師になる夢を持つお子さんのいる広島県の女性はコロナ禍で仕事を失いました。
この2年求職していますが、まだ正社員の仕事は見つかっていません。
「子供に悩みを悟られないよう明るくしていますが、 とりあえずのお金がありません。 大学に行かせてください。子供の教師になる夢を叶えさせてやりたい。」
「生活保護を受ければ良いのでは?」「行政に助けを求めれば良いのでは?」そのような考えもあるでしょう。
しかし、ひとつの手当を受け取ると、他の手当が受けられず、結果として収入が変わらない、もしくは減額となってしまうこともあります。また、行政のサポートにも制限があり、受けるのは簡単でありません。
実際に、すがる思いで生活保護受給の相談をした遺児家庭の方が、市職員の方から、「大学生の娘を持っていることは贅沢品に含まれるので、生活保護の対象にすることができません。」と言われ、断られたことがあったそうです…。
ただ「子どもを大学に行かせてあげたい」という願いは、贅沢なものなのでしょうか?
遺児家庭に寄り添い、奨学金制度で子どもたちの夢を支えるあしなが育英会とは?
これらのご家庭の声は、一般財団法人あしなが育英会が2021年12月4日に発表した遺児家庭の生活状況調査、保護者の方へのオンライン聞き取り調査から拾い上げました。※「コロナの影響 遺児の保護者調査発表会見」
あしなが育英会は、経済的・精神的に遺児たち、およびそのご家庭を支えている非営利の財団法人です。
遺児への経済的な支援として特に大きなものが「奨学金制度」。
高校生以上を対象とし、貸与+給付による奨学金制度を設けています。現在、奨学金を利用して勉学に励んでいる高校生、専門学校生、大学生、大学院生の総数は8千人を超えます。
子どもたちにとっても、その保護者にとっても進学は夢に近づく第一歩です。
経済的困窮から脱するきっかけのひとつとなります。
また、あしなが育英会は、コロナ不況により減収した遺児家庭の窮状を救うため、2020年4月に「遺児の生活と教育の緊急支援金15万円」を奨学生に給付、同年12月には「年越し緊急支援金20万円」を支給しました。出来得る限り遺児家庭に寄り添い支えています。
更に、大学進学後は学生寮「心塾」に入ることで、東京、神戸や大阪の大学に通うことが出来ます。塾費は月1万円で、朝と夕の食事がつき、英語や読書感想文等の指導も受けられます。
また、あしなが育英会では遺児家庭を精神的に支えるため、遺児の心のケア「レインボーハウス」を運営しています。
「レインボーハウス」では同じ境遇の子どもたち同士の交流や、イベントなどを通じて保護者も含め少しずつ前を向いていくサポートをしています。
遺児を対象とした心のケアプログラムは年間100回以上実施しています。
あしなが育英会にも影を落とすコロナ禍の影響とは?

あしなが育英会では、国などからの補助金・助成金は受けず、一般の寄付により全事業を運営しています。
その寄付を募る活動の中で大きいのは、1970年から毎年春・秋に行ってきた「あしなが学生募金」。
参加者は学生・ボランティア合わせて毎回延べ1万人ほどで、全国200か所の街頭で遺児のための奨学金を募ってきました。
同時に、遺児学生たちが勇気を振り絞り、経済的事情で進学が困難な状況を「社会問題」として街頭で訴えてきました。
しかしコロナ禍の影響で2020年から中止となり、街頭募金やそれに触発された一般の方々からの寄附が低調となりました。※2021年12月に2年ぶりに実施
一方、コロナ禍により、奨学金を必要とする遺児が急増し、2019年に約6,500名だった奨学生は、2021年度には過去最多の8,325名に増えました。
進学を控える高校3年生の大学奨学金予約申請者数も過去最多であり、奨学金を支給するための必要資金が大きく膨らんでいます。
たとえコロナが収束したとしても、雇用状況がすぐに回復するとは思われません。したがって、困窮してしまう遺児家庭がさらに増えていく可能性もあります。
奨学金を必要とする学生も更に増えて行くでしょう。
遺児たちが進学の夢を実現し、遺児家庭が経済的困窮から脱するために、あしなが育英会はこれからも多くの遺児と遺児家庭を支えていきます。そのためには、さらに多くの皆さまからのご支援を必要としています。
最後に、あしなが育英会の支援を受けた子どもたちや保護者からのメッセージをご紹介します!(※)
 ●奨学生 えりさん(仮名)
●奨学生 えりさん(仮名)両親を亡くした私に、高校の先生があしなが育英会のことを教えてくれ、学生寮の「心塾」で暮らすことになりました。そこで、留学生との共同生活や、学生募金のクラウドファウンディングなど、数え切れないくらい多くの貴重な経験ができ、かけがえのない親友をつくることができました。
 ●奨学生 ゆうきさん(仮名)
●奨学生 ゆうきさん(仮名)小学3年生の時に発生した東日本大震災で母と二人の妹をなくし、あしなが育英会が提供する心のケアプログラムに参加しました。そこは自分の素を出せて、一人じゃないんだと実感できる安らぎの場所でした。今度は私が、自分と同じような遺児たちを支援する側になりたいと思います。
 ●保護者 佐藤さん(仮名)
●保護者 佐藤さん(仮名)事故で夫を亡くし、二人の子どもを育てる中で、偶然、あしなが育英会と出会いました。同年代の親御さんたちとつながることができ、少しずつ笑顔の自分、本当の自分を取り戻すことができました。日々の感情を忘れることができ、心のケアが出来たのはこの場所だけです。
私たちの小さな積み重ねが確実に子どもの笑顔に、子どもたちの未来につながります。
あしなが育英会は、本当に信頼できる寄付先なのか?
最後に、「あしなが育英会」が寄付先として信頼できるか不安、、、という方もいらっしゃると思いますので、寄付アドバイザーの河合さんの視点で「あしなが育英会」の注目ポイントを解説してもらいました。


あしなが育英会は、病気や災害、自死(自殺)などで親を亡くした子どもたちや、障がいなどで親が働けない家庭の子どもたちを奨学金、教育支援、心のケアで支えています。心のケアの活動では、全国5か所にグリーフケアを行うレインボーハウスを建設しています。
また、日本だけにとどまらず、海外の遺児支援も行っています。
定額寄付では、寄付の使い道を指定することも可能。
あしなが育英会は、活動を通してやさしさの連鎖を世界中に広げながら人間の尊厳が脅かされることのない社会を目指しています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- 「あしなが運動」は50年以上の歴史をもち、遺児を支え続けている
- 交通事故の被害者が築き上げた「被害者立(りつ)」の活動
- 自分たちが受けた恩を後輩たちにも送り届けたいという「恩送りの心」で支援の輪を広げている
『あしなが育英会』は寄付アドバイザーからも、信頼できるおすすめの団体のようです。
寄付を迷っている方は、この機会に支援をはじめてみるのもよいのではないでしょうか。
支援についてのよくある疑問
支援について寄せられるよくある質問をまとめてみました。
Q1:なぜ支援が必要なの?
寄付などの支援は、よりよい社会や困っている人の支援につながります。子どもの貧困や災害、世界の格差など多くの社会問題は、国や行政だけでは解決することは困難です。私たち一人ひとりが、自分事として考え、寄付することによってより良い社会になります。
またこのような社会問題は、明日明後日に解決することはありません。問題解決に取り組む団体は、長期的に事業を作ること必要になってきます。そのため継続寄付のように、長期的に安定したサポートがあることが解決のために大切です。
Q2:支援をする人はなんでするの?
寄付などの支援をする人にはさまざまな理由があります。困っている人を助けたいという人や社会や誰かのためという人、過去に自分も困っていたから恩返ししたいという人もいます。どんなきっかけや理由でも、困っている人の支援になれるのが寄付の魅力です。
あなたにオススメ!別の活動団体の「寄付金でできること」
■相談窓口
・日本いのちの電話連盟
電話0570-783-556(午前10時~午後10時)
https://www.inochinodenwa.org/
・厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」やSNS相談
電話0570-064-556(対応時間は自治体により異なる)
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
・東京自殺防止センター(NPO法人国際ビフレンダーズ)
電話03-5286-9090(午後8時~午前2時半)
https://www.befrienders-jpn.org/
・よりそいホットライン
電話0120-279-338(24時間対応。岩手、宮城、福島3県は末尾3桁が226)
https://www.since2011.net/yorisoi/