日本では7人に1人。「貧困」が理由で夢を諦めてしまう子どもたちがいる現実。
日本は先進国でありながら「子どもの貧困率」が高く、貧困家庭で育つ子どもへの影響が問題となっています。 実に7人に1人の子どもが貧困の状態にあるといわれており、これは世界的にみても最悪のレベルです。
出典:厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」/OECD(2016)Family database”Child poverty”
貧困が子どもへ及ぼす影響は大きく、学費の支払いが困難なために高校や大学への進学を諦め、就職する道を選ぶ人も少なくありません。
やりたい仕事に就けないなど、子どもたちが夢を諦めなければいけない現実があります。
コロナ禍でお母さんが失業…経済的に苦しく不安定な「みどりさんの生活」
みどりさんが中学3年生の3月、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で学校が休校となりました。
4月から晴れて高校生、頑張って合格した学校に通うのを楽しみにしていた矢先の出来事でした。
みどりさんは、お母さんと弟の3人で生活しています。お母さんは病気を抱えながら、それでも一生懸命に飲食店で仕事をし家族3人で力を合わせて暮らしてきました。
ところが、新型コロナウイルスの影響で自粛生活となり、お母さんが働く飲食店は経営が悪化。ついにはお母さんは仕事を失うこととなってしまいました。
もともと病気がちだったお母さんは、心の浮き沈みが激しくなり、家に引きこもりがちになっていきました。
人一倍責任感の強いみどりさんは、不安を抱えるお母さんのためにも、食事作りや家事のすべてを担うようになりました。

そんな中、緊急事態宣言が発せられ、長い自粛生活を余儀なくされます。せっかく受験勉強をがんばって合格した高校にも、当時はまだ通う目処が立っていませんでした。
「この状況はいつまで続くのだろう…」
家族を支えようと精一杯努力を続けてきましたが、お母さんの体調も悪化し、小学生の弟も心が不安定になっていきました。
今まで以上にみどりさんの負担が増えていき、疲弊したみどりさんは食事を作ることもままならなくなっていきました。食べ物が喉を通らない日々が続くようになりました。
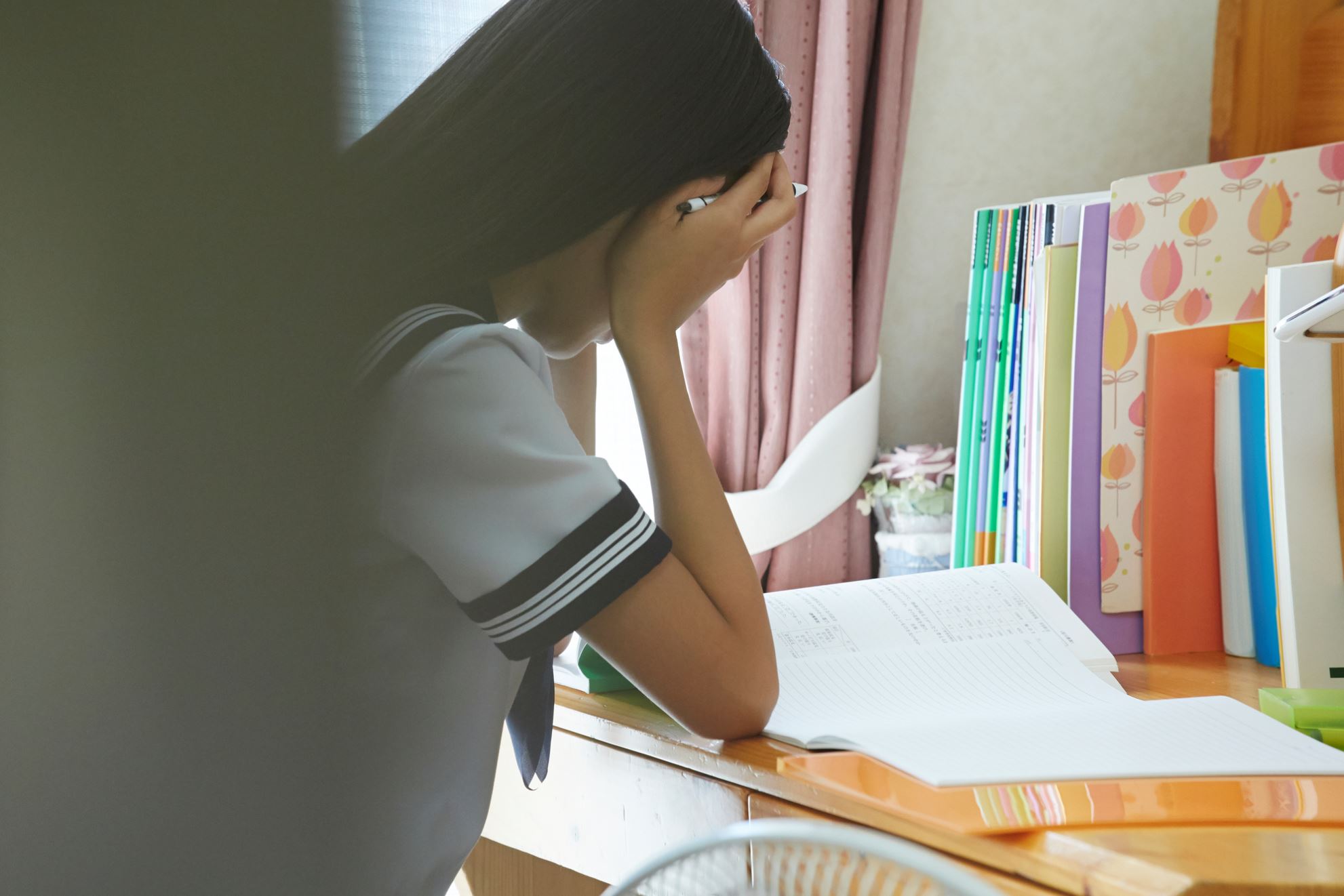
「もう、限界かもしれない…」
みどりさんの窮地に「放課後学校」のスタッフからの連絡
みどりさんは新型コロナウイルスが広がる前、認定NPO法人「カタリバ」が運営する『放課後学校』に通っていました。
そこでは、みどりさんと似たような環境で育ち、同じ悩みを持つ子どもがたくさん居て…。親身になって話を聞いてくれるNPOスタッフやボランティアの方々が居て…。
温かいごはんが食べられたり、一人ひとりに寄り添って勉強を教えてくれる、みどりさんにとって安心できる第3の居場所でした。
みどりさんは『放課後学校』に定期的に通っていましたが、コロナ禍になり、お母さんのことや家庭での家事に時間も気力も注いでいたため、放課後学校へ連絡する余裕すら失くしていました。
そんなある日、放課後学校を運営するNPOスタッフからメッセージが来ていることに気づきました。

「私たちからの連絡見てるかな? 毎日、お弁当を配っているから、取りに来ていいんだよ!」
この呼びかけに、みどりさんはひとり苦しんでいたことを誰かが見守ってくれていたような気持ちになりました。それからみどりさんは、毎日のようにお弁当を取りに行くようになりました。
お弁当はとてもバランスの取れた内容で、お腹も満たされ、食事を作る負担も減り、生活のリズムを少しずつ取り戻せていきました。
また、お弁当を取りに行く時に、放課後学校のスタッフ達に今の苦しさを話すだけで、少しずつ楽になっていることにも気づきました。
次第にお母さんの状態も少しずつ改善し、弟と遊んであげられる時間も増えました。現在お母さんは新しい仕事を探し始めています。
みどりさんの通う放課後学校とは
みどりさんが通っている、認定NPO法人「カタリバ」が運営している『放課後学校』。
通常時は、週6日、平日の夕方と、休日の日中の時間帯に子どもたちを迎えています。
コロナ禍において、以下の活動を行っています。
・生活困窮世帯へのお弁当の配布
・定期的なビデオ通話での見守り
・オンラインでの学習支援
・パソコン機器の無償貸与

これまで誰にも不安や悩みを話せず、家で孤独に耐えていた子どもたちにとって、生活や将来への不安をスタッフに親身になって聞いてもらい、受け入れてもらえることが喜びとなり、新たな活力となります。
放課後学校では孤独や不安を抱える子どもたちに安心してもらえる関係性を築き、安らぎと明日への力を得るかけがえのない場所となっています。
オンラインでの授業や、スタッフとの対話によるみどりさんの変化

少しずつ時間に余裕を持てるようになったみどりさんは、「カタリバ」からパソコンを貸してもらい、『オンライン学習』に取り組んでいます。
わからないところがあれば、パソコンのビデオ通話で、気軽にスタッフに相談することができます。勉強だけでなく、パソコンの画面越しに家庭の状況を話せることは、みどりさんの心を穏やかにしてくれました。
まだ完全に家庭が安定しているとは言えず、高校も完全に再開はしていないので不安はありますが、前向きに過ごせるようになってきているようです。
最後に、支援を受けた子どもたちからのメッセージをご紹介します。(※)
 ●ご飯が1番の楽しみ
●ご飯が1番の楽しみ放課後学校に通いはじめてから、高いお金をおかけなくても、いろいろなことに挑戦できるということを知りました。私が一番楽しみにしているのはご飯です。お腹いっぱい食べて、幸せな気分になったあと、また勉強を頑張ることができます。放課後学校のおかげで、私達の興味は広がり、未来も広がり続けています。
 ●放課後学校は心の居場所です
●放課後学校は心の居場所です放課後学校は、私の知らない世界を見せてくれたり、出会ったことのない人と巡り合わせてくれました。そんな経験をして、私の考え方は変わりました。自分のはるか上にあるような高校を目指し、結果、希望の学校に入学することができました。放課後学校と出会ったことで、勉強を頑張ることができたのはもちろんのこと、たくさんの人に出会い、たくさんの気持ちを知ることができました。
私たちの小さな積み重ねが確かに子どもの笑顔に、子どもたちの未来につながります。
カタリバは、本当に信頼できる寄付先なのか?
最後に、「カタリバ」が寄付先として信頼できるか不安、、、という方もいらっしゃると思いますので、寄付アドバイザーの河合さんの視点で「カタリバ」の注目ポイントを解説してもらいました。

カタリバは、自身ではどうすることもできない家庭環境などの課題を抱える子どもたちを対象に、居場所・学習・食事を地域と連携しながら届ける活動などを行っています。
活動を始めたきっかけは、東日本大震災。最近ではコロナの影響を受ける子どもの支援も開始し、日本中の子ども達が、生まれ育った環境や家庭などの格差によって、可能性を閉ざされてしまうことが決してないように支援を続けています。
また、カタリバは、東京都から認証を受けた認定NPO法人であり、1万を超える個人・企業からも支援を受けており受賞歴も豊富です。
活動を通じて「すべての10代が意欲と創造性を育める未来」の実現を目指しています。
寄付アドバイザーが見た注目ポイント!
- 「ナナメの関係という共成長モデル」「10代に伴走」「個人の成長を支える強い組織文化」が強み
- 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探求学習の実践支援などの活動を、全国で展開
- 活動に関わった10代の声の紹介、カタリバの仲間紹介、支援者/企業紹介など、いろんな人や支援者の関わりの特徴が伝わってくる
『カタリバ』は寄付アドバイザーからも、信頼できるおすすめの団体のようです。
寄付を迷っている方は、この機会に支援をはじめてみるのもよいのではないでしょうか。
支援についてのよくある疑問
支援について寄せられるよくある質問をまとめてみました。
Q1:なぜ支援が必要なの?
寄付などの支援は、よりよい社会や困っている人の支援につながります。子どもの貧困や災害、世界の格差など多くの社会問題は、国や行政だけでは解決することは困難です。私たち一人ひとりが、自分事として考え、寄付することによってより良い社会になります。
またこのような社会問題は、明日明後日に解決することはありません。問題解決に取り組む団体は、長期的に事業を作ること必要になってきます。そのため継続寄付のように、長期的に安定したサポートがあることが解決のために大切です。
Q2:支援をする人はなんでするの?
寄付などの支援をする人にはさまざまな理由があります。困っている人を助けたいという人や社会や誰かのためという人、過去に自分も困っていたから恩返ししたいという人もいます。どんなきっかけや理由でも、困っている人の支援になれるのが寄付の魅力です。
※写真はすべてイメージです。


