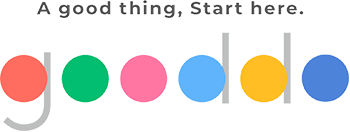記事提供:ケノコト

子どもたちは自分が生まれ育つ環境を選べません。
親や家庭の状況によらず、すべての子どもたちが社会から孤立することなく「安心・安全」にそして愛されて暮らしていけたら。
子どもは未来の宝です。ないがしろにされていい子どもなんて誰一人いないはずですから。
日本の子どもたちの今
地域のつながりや、親族とのつながりが希薄になり、無縁社会となってきています。そんな環境の中で、親の経済状況や社会とのつながりが、子どもが得られる教育や愛情、社会的資源に直接左右されるようになりました。
十分な所得がなかったり、十分な教育や教養を身に着けられていない、または人とのつながりが希薄な親は、
親自身が孤立しやすく、子どもたちに必要な社会資源を提供することは難しくなってしまいます。
それに加えて、DV等による離婚や、養育費が十分に支払われない、親と絶縁状態である等、親自身の家庭環境によっては社会的・経済的孤立をさらに助長させることにもなります。

民間主体の動きを
子どもの社会保障や権利保障を、行政か家庭だけに任せるのではなく、昔の地域感のつながりのように、民間や市民主体で解決を担っていくために、子どもたちに関わる大人を増やしていってみてはどうでしょう。
「こんにちは。どこかへお出かけかな?」
そんな言葉をさりげなく、当たり前に口にできる繋がりが、子どもたちを見守っていくセーフティーネットになるのではないでしょうか。
子どもを取り巻く現状を社会に伝え、親や行政以外の見守り役として、子どもたちを導き、そして伸ばしていく大人たちが増えたら、子どもたちを守っていけるのではないでしょうか。

どんな環境で生まれ育っても蔑ろにされて良い子どもたちはいません。
未来の宝である子どもたちは、みな平等に教育を受け、愛情を受け、等しく権利を有するのはずですから。
誰かひとりが頑張るのではなく、自分の時間を割く人、寄付で支える人、教材やプログラムを提供する企業、活動を応援し発信してくれる人など、それぞれの分野で「子どもたちを応援していく」ことができたら、社会全体が子どもたちを育てることになります。

子どもの問題は親がやるべき、子どもの問題は学校がやるべき、などと誰かに責任を押し付けるのではなく、1人ひとりができることを行い、実行していけたらきっと、子どもたちの等しい幸せを叶えられるのではないでしょうか。
子どもは未来の宝。
さぁ、できることから始めてみませんか?
「こんにちは。どこかへお出かけかな?」
そんな言葉をさりげなく、当たり前に口にできる繋がりが、子どもたちを見守っていくセーフティーネットになるのではないでしょうか。
子どもを取り巻く現状を社会に伝え、親や行政以外の見守り役として、子どもたちを導き、そして伸ばしていく大人たちが増えたら、子どもたちを守っていけるのではないでしょうか。

ないがしろにされていい子どもたちなんて、いない
どんな環境で生まれ育っても蔑ろにされて良い子どもたちはいません。
未来の宝である子どもたちは、みな平等に教育を受け、愛情を受け、等しく権利を有するのはずですから。
誰か一人が頑張るのではなく、社会全体で見守る
誰かひとりが頑張るのではなく、自分の時間を割く人、寄付で支える人、教材やプログラムを提供する企業、活動を応援し発信してくれる人など、それぞれの分野で「子どもたちを応援していく」ことができたら、社会全体が子どもたちを育てることになります。

子どもの問題は親がやるべき、子どもの問題は学校がやるべき、などと誰かに責任を押し付けるのではなく、1人ひとりができることを行い、実行していけたらきっと、子どもたちの等しい幸せを叶えられるのではないでしょうか。
子どもは未来の宝。
さぁ、できることから始めてみませんか?