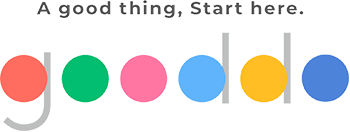記事提供:ケノコト

共働きが当たり前となってきたことで、妊娠や出産を経てもまた、仕事に復帰できる女性が増えてきました。
そこで問題となるのが保育園事情。働きたくても預け先がない、預けられたはいいけど子供が熱をだして仕事に行けない。そしてある人は、子どもに障害があるというだけで、保育園に預けられない。
待機児童問題だけでなく、核家族化の中で孤独な子育てが加速し、虐待や見えない貧困をはじめ、起こるべきでない悲しいニュースまで聞こえてきます。このようにリアルな「子どもや親子を取り巻く社会問題」はまだまだたくさんあるのが現状なのです。
子育てしている方もそうでない方も、未来の子どもたちのために、子育てを取り巻く社会問題にすこし関心を寄せてみませんか。
障害児のための保育園って?
子どもを預ける場所がないために、就労を希望しながらも、働けない障害児の保護者が潜在的に存在します。
全国の健常児を持つ母親の常勤雇用率が34%あるのに比べ、障害児の母親の常勤雇用率はわずが5%、7分の1しかありません。
一方で、新生児医療の発展により、救える命が増えて医療的ケアを必要とする子どもは増加傾向にあります。

なぜ障害のある子どもの親は仕事を辞めるのか。重い障害がある子どもを預かれる場所が極端に少ないからです。さらに痰の吸引やチューブでの経管栄養などの医療的ケアと保護者の就労を前提とした長時間保育を両立する施設は今までありませんでした。
そんな中、NPO法人フローレンスは、日本で初めての医療的ケア児の長時間保育を行う「障害児保育園ヘレン」を2014年に東京都・杉並区に開園しました。
開園以来、潜在的ニーズによりたくさんの入園希望があり、2016年7月には2園目となる保育園を東京都・豊島区に開園します。

一方で、子どもが欲しいと切に願い不妊治療に取り組む夫婦もたくさんいます。大切な希望である赤ちゃんの命を救うために「赤ちゃん縁組」という取り組みがあります。妊娠期から相談に乗り、どうしても育てられない場合には出産と同時に、子どもを望む育ての親に託すという取り組みです。
双方がお互い解決できる道筋をつくることで、赤ちゃんの命が救えるかもしれません。
意外と思われる方が多いかもしれませんが、いま日本では6人に1人の子どもが貧困にあると言われています。
とりわけ、母子家庭では56%が貧困にあると言われており、母子家庭の71%が収入200万円未満と、経済的に非常に厳しい状況に置かれています。
学費が高額な日本では、親の経済状況が子どもの教育機会の減少、そして子の将来に渡る貧困につながり、世代をまたがる貧困の連鎖がおきています。
働いて子どもたちにご飯を食べさせたいのに、預け先が高額で預けられずに働けない。それでは負の連鎖は起こるばかりです。低所得のひとり親家庭が、金銭面の心配なく預けられ就労することが、経済的自立を促し親子の将来にもつながるのではないでしょうか。
認定NPO法人フローレンスでは、2008年からひとり親家庭に安価で病児保育サービスを提供することで、ひとり親家庭をサポートしています。

子どもは社会のたからものだからこそ、どの子どもにも均等に未来を与えていきたいですね。そのきっかけは社会を動かすわたしたち大人がつくりあげていくものですから。
全国の健常児を持つ母親の常勤雇用率が34%あるのに比べ、障害児の母親の常勤雇用率はわずが5%、7分の1しかありません。
一方で、新生児医療の発展により、救える命が増えて医療的ケアを必要とする子どもは増加傾向にあります。

障害の有無にかかわらず、全ての子どもが保育を受け、保護者が働くことを選択できる社会
そんな中、NPO法人フローレンスは、日本で初めての医療的ケア児の長時間保育を行う「障害児保育園ヘレン」を2014年に東京都・杉並区に開園しました。
開園以来、潜在的ニーズによりたくさんの入園希望があり、2016年7月には2園目となる保育園を東京都・豊島区に開園します。

赤ちゃんの命を守る「赤ちゃん縁組」
生まれたばかりの赤ちゃんが、2週間に1人命を落としています。その背景には「望まない妊娠」があります。貧困、性犯罪の被害など様々な事情を背負い、相談できずに孤立した女性が、生後間もないわが子を自ら殺してしまう−そんな悲劇が今この日本で起きています。
一方で、子どもが欲しいと切に願い不妊治療に取り組む夫婦もたくさんいます。大切な希望である赤ちゃんの命を救うために「赤ちゃん縁組」という取り組みがあります。妊娠期から相談に乗り、どうしても育てられない場合には出産と同時に、子どもを望む育ての親に託すという取り組みです。
双方がお互い解決できる道筋をつくることで、赤ちゃんの命が救えるかもしれません。
障害の有無にかかわらず、全ての子どもが保育を受け、保護者が働くことを選択できる社会
意外と思われる方が多いかもしれませんが、いま日本では6人に1人の子どもが貧困にあると言われています。
とりわけ、母子家庭では56%が貧困にあると言われており、母子家庭の71%が収入200万円未満と、経済的に非常に厳しい状況に置かれています。
学費が高額な日本では、親の経済状況が子どもの教育機会の減少、そして子の将来に渡る貧困につながり、世代をまたがる貧困の連鎖がおきています。
働いて子どもたちにご飯を食べさせたいのに、預け先が高額で預けられずに働けない。それでは負の連鎖は起こるばかりです。低所得のひとり親家庭が、金銭面の心配なく預けられ就労することが、経済的自立を促し親子の将来にもつながるのではないでしょうか。
認定NPO法人フローレンスでは、2008年からひとり親家庭に安価で病児保育サービスを提供することで、ひとり親家庭をサポートしています。

子どもは社会のたからものだからこそ、どの子どもにも均等に未来を与えていきたいですね。そのきっかけは社会を動かすわたしたち大人がつくりあげていくものですから。