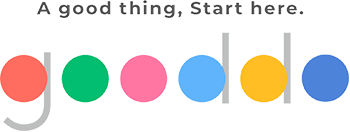記事提供:ケノコト

子どもは未来へのたからもの。
家庭の中だけでなく、幼稚園、学校、地域など社会全体で育て上げていく事が大切ですよね。
教えて育てる、と書いて「教育」と読みます。学校だけが教育の場ではなく社会そのものが教育になりうる場。
子どもたちの未来のために、教育について少し考えてみたいと思います。
教育環境の格差が日本にもあるんです
多くの子ども・若者が、家庭の所得や住む地域に関わりなく、学校に通える。
教育機会が平等に行き届いていると言われるこの日本でも、目に見えにくい「機会格差」が存在しています。
子どもや若者の意欲や能力が、生まれ育った環境によって左右されてしまうなんてなんだか不公平です。

どんな環境にいても、「未来は自分自身で創り出せる」という期待感を持ち続けられることが大切です。自ら目標を定めて目の前の「やるべきこと」から、逃げずに向き合うこと。向き合って取り組むことで、自信にもつながっていきます。
周りを思いやり、「地域」や「社会」などコミュニティのため共に助け合うよう働きかけます。そのためには大人も一緒になって背中を見せることが大切です。他の誰かによる環境の改善を期待するのではなく、本人が参画することで共生の意味を知るようになります。
これからの時代がどのように変化しても、自ら考え、新しい課題を見つけること。柔軟な頭をもつことです。自分が舵取りをする気持ちでその解決に向け進んでいくことが新しい価値を産み出していけるのです。

昔は「近所のおじさんに怒られる」という事は当たり前の光景でしたが、現在は子どもが少なく手塩にかけて育てられるので叱られる経験も少ないそうです。
子どもも、若者も、大人も、一緒になって輪の中に入れる社会やコミュニティがあったら、少しは変わってくるのではないでしょうか。
年齢関係なく接する事で、子どもは昔の知恵を知る事ができ、生きる術を身につけ、常識を得る。それだけでなく大人自身もどこかで忘れてきた心を子どもから気づかされる事もあるのです。
学校や家庭、地域だけでなく、新しいコミュニティの場所。社会全体が子どもの未来をつくります。
育て、教え、育む「教育」。子どもたちの未来のために、わたしたち大人も社会づくりから参画していきたいですね。
下記にご紹介するNPO法人カタリバは、子どもたちが「未来は自分でつくれる」と信じられる社会を目指し、活動する教育NPOです。
子どもたちのために何かしたいという方は、まずはこうしたNPOの取り組みについて知ることも大きなアクションのひとつですね。
教育機会が平等に行き届いていると言われるこの日本でも、目に見えにくい「機会格差」が存在しています。
子どもや若者の意欲や能力が、生まれ育った環境によって左右されてしまうなんてなんだか不公平です。

社会を「生き抜く力」って何だろう?
これからの未来、困難が待ち受けていても、子どもたちが社会で生き抜いていける力とはなんでしょうか。子どもたちが思い描いた未来を自分で創り広げていける力を作るために必要なことは何でしょうか。
1.自律する気持ちを育もう
どんな環境にいても、「未来は自分自身で創り出せる」という期待感を持ち続けられることが大切です。自ら目標を定めて目の前の「やるべきこと」から、逃げずに向き合うこと。向き合って取り組むことで、自信にもつながっていきます。
2.共に生きるんだという意識をもたせる
周りを思いやり、「地域」や「社会」などコミュニティのため共に助け合うよう働きかけます。そのためには大人も一緒になって背中を見せることが大切です。他の誰かによる環境の改善を期待するのではなく、本人が参画することで共生の意味を知るようになります。
3.臨機応変に考える
これからの時代がどのように変化しても、自ら考え、新しい課題を見つけること。柔軟な頭をもつことです。自分が舵取りをする気持ちでその解決に向け進んでいくことが新しい価値を産み出していけるのです。

社会が子どもを守り、社会が子どもをつくる
核家族化や少子高齢化が進み、今の子どもたちは大人と接する機会が昔より少なくなりました。
昔は「近所のおじさんに怒られる」という事は当たり前の光景でしたが、現在は子どもが少なく手塩にかけて育てられるので叱られる経験も少ないそうです。
子どもも、若者も、大人も、一緒になって輪の中に入れる社会やコミュニティがあったら、少しは変わってくるのではないでしょうか。
年齢関係なく接する事で、子どもは昔の知恵を知る事ができ、生きる術を身につけ、常識を得る。それだけでなく大人自身もどこかで忘れてきた心を子どもから気づかされる事もあるのです。
学校や家庭、地域だけでなく、新しいコミュニティの場所。社会全体が子どもの未来をつくります。
育て、教え、育む「教育」。子どもたちの未来のために、わたしたち大人も社会づくりから参画していきたいですね。
下記にご紹介するNPO法人カタリバは、子どもたちが「未来は自分でつくれる」と信じられる社会を目指し、活動する教育NPOです。
子どもたちのために何かしたいという方は、まずはこうしたNPOの取り組みについて知ることも大きなアクションのひとつですね。